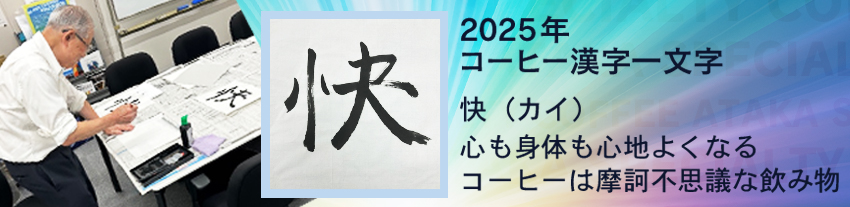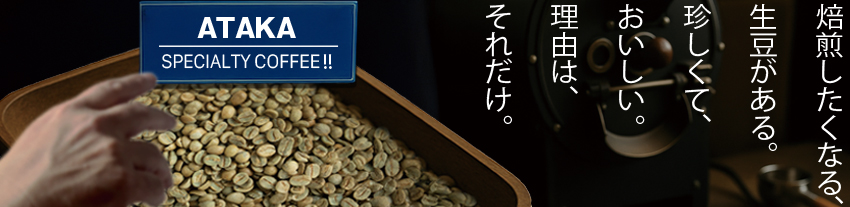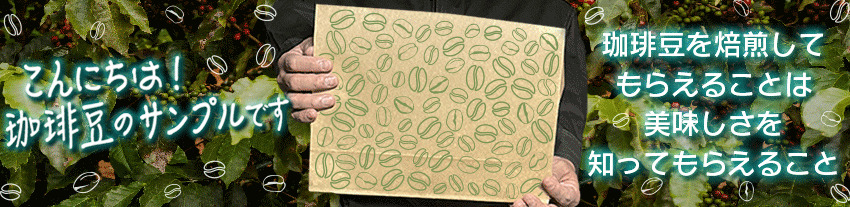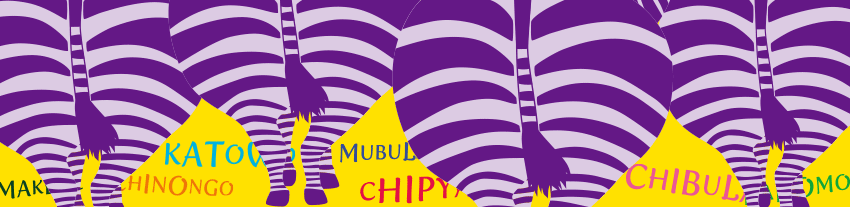2019/10/01
(NO.1184) シマフクロウ デコッパチ
「人間のコントロールを超えた、決して後戻りのできない連鎖反応が始まるリスクがあります。50%という数字は、あなた方にとっては受け入れられるものなのかもしれません。しかし、この数字は、(気候変動が急激に進む転換点を意味する)「ティッピング・ポイント」や、変化が変化を呼ぶ相乗効果、有毒な大気汚染に隠されたさらなる温暖化、そして公平性や「気候正義」という側面が含まれていません。この数字は、私たちの世代が、何千億トンもの二酸化炭素を今は存在すらしない技術で吸収することをあてにしているのです。」 (国連の温暖化対策サミット。スウェーデンの16歳の活動家、グレタ・トゥーンベリさん演説より)
日本には、梟(ふくろう)という存在にとりつかれた人が意外と多い。今年の1月に、わたしは、厳冬の八ケ岳の山麓で、夕方まで数時間、その姿を探したが、結局、求めていた姿をみることはできず、であった。この時は、黙々と、お互いに(フクロウ、ミミズクはきましたか? あそこにみえるのはノリス(タカ科)ですよねー、などと)声を掛け合いながら、待ち続ける人間たちの姿・生態を見に行ったようなものであった。南アルプスや、長野・山梨県境、八ケ岳に囲まれた盆地状の高原で、言葉にならない寒さのなか、カメラや望遠鏡を抱えて、ひたすら、ひたすらに待つ人々の姿のほうに、少なからず驚愕を覚えた。
その後、5月に知床半島の梟ウォッチに行ってみた。夜に7、8時間待つことも厭わない人達が集まる場所である。そのときは、やっとフクロウと会えることができたが、ちゃんとした機材(フラッシュなしで、望遠で、夜の梟を撮影できるカメラやレンズなど)を持ってきていないのは、うちの家族ぐらいであった。私が、数十メートル先からケイタイで撮った動画はお世辞にも素晴らしいとは言えないが、それでも、シマフクロウの姿はやや神々しくもあり、今でもその映像を時々、しみじみとみている。
知床半島の羅臼町。少しだけ海から離れると、そこはすでに、東京では考えられないほどの闇である。夜7時半から、翌朝6時までの間にシマフクロウがみることができれば、ラッキーですねと、スタッフの方に言われる。一つの川における相当広い地域に一つのつがいが生きる。しかし、ここのオスは相当な気まぐれ者で、毎日、エサを運んでくるとは限らないとのことである。絶滅危惧種にしては、呑気なんだなぁと思うものの、彼にもいろいろと事情があるのだろうし、彼らのテリトリーにお邪魔しているのは、こちらの方である。
アイヌ語では、村の守り神と呼ばれるシマフクロウは、梟のなかでも、最大級の大きさをほこるが、現在は、北海道にしか生息していない。以前は、道内に約千羽生息していたというが、一時、70羽ほどに減り、いまは200羽弱と推察されるそうだ。繊細さ、頭のよさは抜群。飢えても気丈に振る舞い、餓死してしまう例もあるという。
夜3時を過ぎ、もう諦めかけ、幾人もが仮眠をとりに、部屋やクルマにもどる。わたしも、諦めかけた。もう帰ろうよ、わたしはもう限界なのである、と言おうとしたら、明け方近くに、鳴き声らしきものが山から突然聞こえた。オスがどこからともなく、舞いおりてきた。10分くらいは、川洲にいたであろうか。
なぜ、ひとは、梟にとりつかれるのか? シマフクロウの姿を求めて、職を変えたり、北海道に移り住む人も少なくないようだ。シマフクロウの生存の前提は、とてつもない自然があること。そのような環境がなくなると、それは、人間もいずれ生きられないことにつながることを暗示しているかもしれない。また、シマフクロウの持つ、けだかさ、気まぐれさ、神経質さ、なども、人を魅了するのか。こちらは当然のごとく振り回されるのみ。その誇り高さは、20世紀を代表するソプラノ歌手、マリア・カラスをも凌ぐくらいである。シマフクロウは、その翼を広げると数メートルにおよぶ。まさに、ヒトは息を飲み、息ができなくなる。わまり数十メートルの雰囲気を、一瞬にして変えてしまう。
2019年10月1日 デコッパチ
◆最近の ピリオドの向こう側
- 2025/12/25(NO.1794) 詐欺とクマ! 小濱綱之
- 2025/12/22(NO.1793) あなた死んでもいいですか 山田雄正
- 2025/12/17(NO.1792) なめたらいかんぜよ! 小濱綱之
- 2025/12/15(NO.1791) わが身の業も煮ゆるかな 山田雄正
- 2025/12/09(NO.1790) 生きている不思議 山田雄正
- 2025/12/08(NO.1789) スパルタ デコッパチ
- 2025/12/05(NO.1788) おなごの勘! 小濱綱之
- 2025/12/04(NO.1787) ゲイシャの味は産地による 岡 希太郎
- 2025/12/01(NO.1786) 自堕落に生きながらえて 山田雄正
- 2025/11/26(NO.1785) まともじゃない! 小濱綱之
>>リスト表示