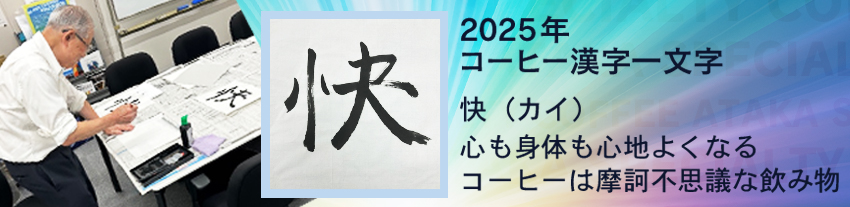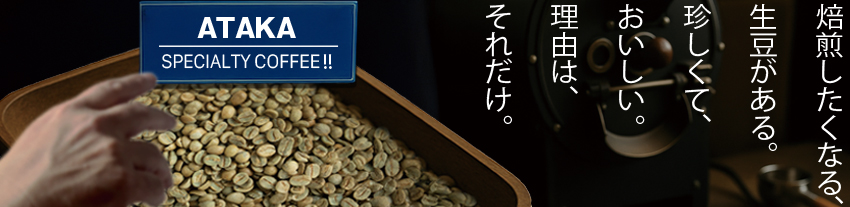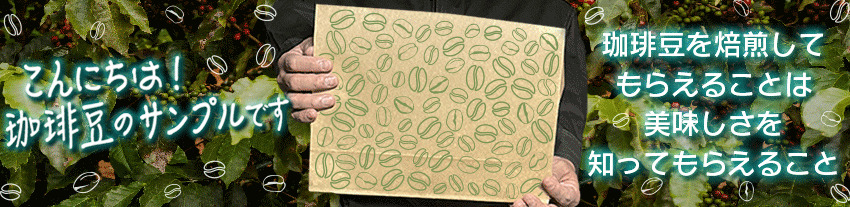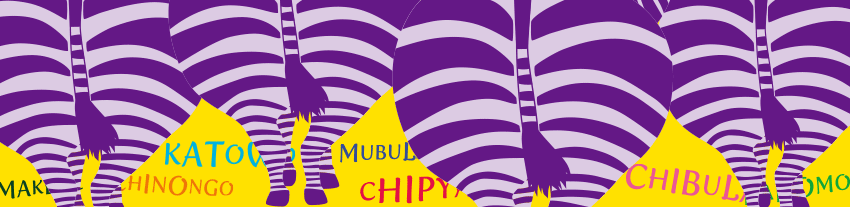2020/12/10
(NO.1243) 白洲正子 デコッパチ
随筆家の白洲正子(1910-1998)は白洲次郎(実業家)の妻である。二人とも、どうひかえめに見ても、かなり濃い人生を送った。先日、本棚に数年ほったらかしておいた「白洲正子自伝」の頁を開いてしまい、「規格外のお嬢様」の、示現流な生涯を垣間見ることとなる。
自伝の冒頭は、白洲正子の祖父の逸話から始まるが、いまの世ではありえないような話からはじまる。何人かの女流小説家を読んだが、こんな冒頭で自伝が始まる例はみたことがない。
少し刺激が強いので、詳しくは書けないが、幕末に京都で、薩摩藩の侍Aが祇園で見廻組に討たれた。それを前にして、遁走してしまった何某がいた。彼が指宿における侍Aの葬儀に現れ、焼香をする。ある気性の激しい若侍、橋口覚之進に呼ばれる。幕末の薩摩の気質、風土を思うと、そのときに何が起きたか想像がつこう。その橋口覚之進こそが、白洲正子の祖父、後の樺山資紀(明治の海軍軍人)である。
なんとも野蛮な話ではある。しかし、そうしなければならない事情もあった。参列者はもとより、全員に、暗黙の了解があったようだ。その後は、静寂のなか、葬儀は執り行われたのではないか、と白洲正子は書く。また、江戸時代が、政治的には連邦制に相当近かったことが、このエピソードには色濃くでている。
最初の一撃に全てをかけるという示現流。能などにのめり込んだ彼女は、剣術はしなかったものの、示現流は彼女の通底をなしている。
自伝を書くタイプではないことは、文面からひしひしと伝わる。しかし、十代のときの留学、社交界、雷に打たれたような恋と結婚、戦中・戦後の青山二郎や小林秀雄といった友人たちとの交流、高まる審美眼、など、豪快で繊細な生涯が綴られている。
本人によると、小学校に入る前に富士山に登りたくてダダをこね、14歳のときに一人で米国に行くと言ってゴネ、結婚の際は、白洲次郎と結婚させなければ家出すると家族を脅かした。しかも、すべてを実現させている。
結婚の経緯もなかなかである。すべてのお見合いを、ことごとく断っていたのに、ある日、十歳ほど上の白洲次郎と出会い、雷に打たれる。結婚とはまことに雷に打たれるようなものだ。世の中には、再婚するひとがいるが、2回以上雷に打たれたということなのだろうか。よくも死なないものだ。
次郎は、1930年前後の大恐慌の影響で、留学先から帰国していたのだ。結婚式は、両家ともに経済的に相当な打撃を受けていたため、こじんまりとしたものであったようだ。
その後も自伝は、戦争中、戦後も脈々と続く。政治・経済界の中枢の一家からみた近代史として貴重な本である。また、個性のかたまり同士の恋愛・結婚小説としても秀逸である。
戦後、ふとあるきっかけで、彼女が銀座で商売を始めるところが面白い。次郎に相談したら、株式会社形式にしたらよかろうと、こころよく賛成する。どうやら、青山二郎や小林秀雄と飲んだくれたり、古美術品の購入熱から、遠のいてくれるものと、夫は期待したようだ。
しかし、白洲次郎の目論見は、まったくうまく行かなかったようである。昭和を動かしたといわれる、偉大な経営者も、奥さんだけは、操縦できなかったのだろうか。算盤にさわったこともなかった彼女のお店は、当初は彼女が知らないところで借金が発生するなどめちゃくちゃであったが、さまざまなトラブルをこえて、やがて軌道に乗っていった。
2020年12月10日 デコッパチ
◆最近の ピリオドの向こう側
- 2026/02/02(NO.1803) 争点、焦点 デコッパチ
- 2026/01/26(NO.1802) 本なんか読まない 山田雄正
- 2026/01/20(NO.1801) 身の丈に合ったスタジアム! 小濱綱之
- 2026/01/19(NO.1800) いつも間違いそして今 山田雄正
- 2026/01/13(NO.1799) 強い奴を倒せ 山田雄正
- 2026/01/13(NO.1798) 詮無いこと! 小濱綱之
- 2026/01/09(NO.1797) 晩餐会、ワイン、コーヒー デコッパチ
- 2026/01/06(NO.1796) コーヒーノキの起源 岡 希太郎
- 2026/01/05(NO.1795) どうなる2026年 山田雄正
- 2025/12/25(NO.1794) 詐欺とクマ! 小濱綱之
>>リスト表示