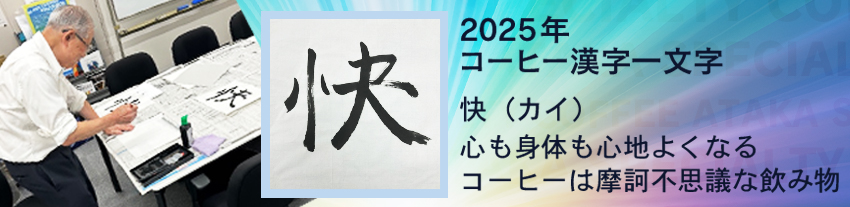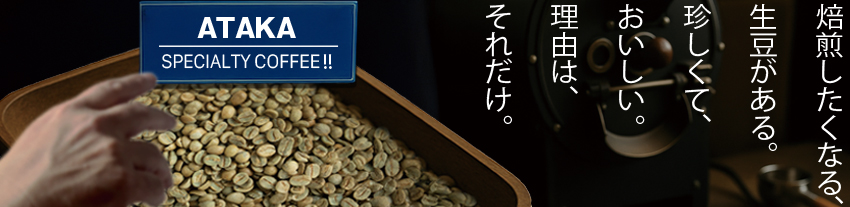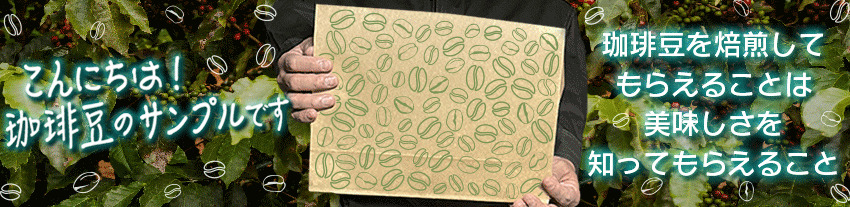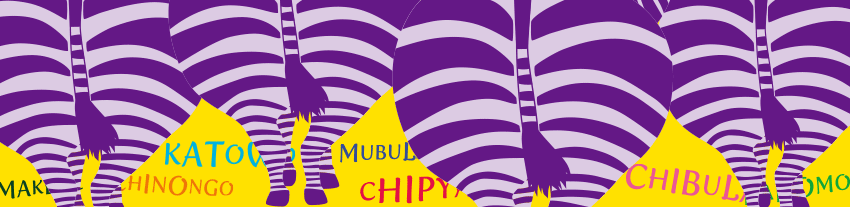2019/08/05
(NO.1177) マラウィ デコッパチ
マラウイ・・・伝統的な農業国であり,労働人口の約80%が農業及び農業関連事業に従事している。タバコ,紅茶,砂糖等の一時農産品が全輸出の8割を占めており,これら農産物価格の国際市況に外貨収支が大きく左右されるため,経済構造の変革や新たな外貨獲得源の確保が課題となっている。GDP 63.0億米ドル、1人当たりGNI 320米ドル(2017年:世銀)(外務省ホームページより)
映画、風をつかまえた少年(2018年、イギリス、マラウイ)。原題は、The boy who harnessed the wind
最近、新潟の苗場山に行こうとして、雨のため、4回くらい登山が延期になったが、この映画をみたら、そんなことは「些細な問題」にさえも、ならないことを痛感せざるをえない。すべては、何事も、水、風があればこそ、なのである。
アフリカの小国マラウイ。当時、人口の2%しか電気を使うことができなかった。アフリカ大陸・大地溝帯の南部、タンザニア、ザンビア、モザンビークの3か国に囲まれた内陸国(面積は日本の3分の1)で、マラウイ湖に面した美しい国である。その国の、ある村で暮らす少年。両親、姉、小さい弟、犬と暮らしている。
農業を営む父。ある年、大雨がおこるが、親族がタバコ業者に木材を売り、森林が薄くなっていたためか、被害洪水が大きくなってしまい、不作になる。そして次に、干ばつがくる。干ばつが続き、再度不作に。学費を払えず、中学側からも、登校を禁止される。
どうやら公立教育制度はないようだ。主人公ウィリアムは、こっそり、授業に出るが、先生に追い出される。この場面は、かなり、やるせない。
しかし、主人公は、図書室になんとかもぐりこみ、電気などの本を、読み漁る。
不作の影響は深刻化していく。町に、大統領が演説に訪れたとき、族長が食糧支援を政府に強く激しく求める。しかし、大統領の機嫌をそこね、こわもてのボディガードたちに引きずりおろされ、殴打され、大怪我を負わされてしまう。この場面も、かなりやるせない。
町は飢餓状態に。主人のいない日に、男たち数人が、家にやってきて、食糧を強奪してゆく。町を出ていくものも、どんどん増えていく。
壊れていくコミュニティー。暴徒化しつつある地域住民。先生たちも、櫛の歯が欠けるように、いなくなっていく。
しかし、家には井戸がある。風もある。最後に、ストーリーは、大きくうねっていく。よかったね、ウィリアムくん!
主人公の少年がなんともキュートである。父親役は、俳優キウェテル・イジョフォー。人によっては、人生感が書き換えられる作品である、「アミスタッド(1997年スピルバーグ監督)」において、印象の強い演技をしている。いまは、もう、頑固な親父、である。
英BBCが制作に絡んでる。ここが関わるドキュメンタリーや、映画は深いと思う。視点の角度が日本人とちょっと違って、掘り下げ方も半端ではないのではないかと、ときどき思う。
アフリカの小さな国における、町が崩壊する一歩手前までを映像体験させられる、骨身にしみる映画だ。ただ、ささやかな希望を言わせていただくと、水で、村が復活していく過程も、ドーンと、もうすこし、鮮やかにみせてほしかったなぁ、と思う。
ケニアの福祉制度に、初動の一歩を穿とうと、働いている、ある医師のスピーチを聴く機会を得るなど、最近は、身の回りで、アフリカの風がそよそよと、吹いている。
2019年8月4日 デコッパチ
◆最近の ピリオドの向こう側
- 2026/01/06(NO.1796) コーヒーノキの起源 岡 希太郎
- 2026/01/05(NO.1795) どうなる2026年 山田雄正
- 2025/12/25(NO.1794) 詐欺とクマ! 小濱綱之
- 2025/12/22(NO.1793) あなた死んでもいいですか 山田雄正
- 2025/12/17(NO.1792) なめたらいかんぜよ! 小濱綱之
- 2025/12/15(NO.1791) わが身の業も煮ゆるかな 山田雄正
- 2025/12/09(NO.1790) 生きている不思議 山田雄正
- 2025/12/08(NO.1789) スパルタ デコッパチ
- 2025/12/05(NO.1788) おなごの勘! 小濱綱之
- 2025/12/04(NO.1787) ゲイシャの味は産地による 岡 希太郎
>>リスト表示