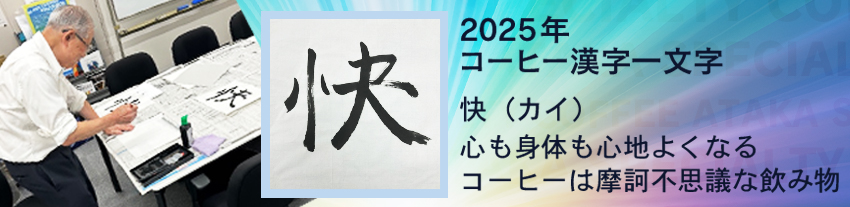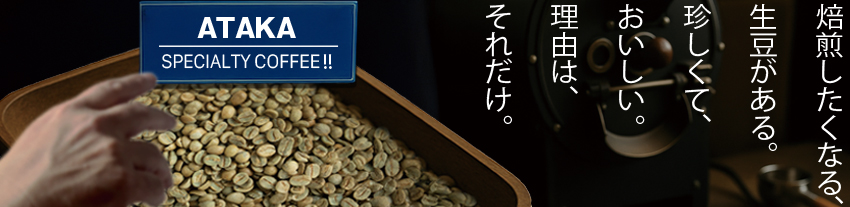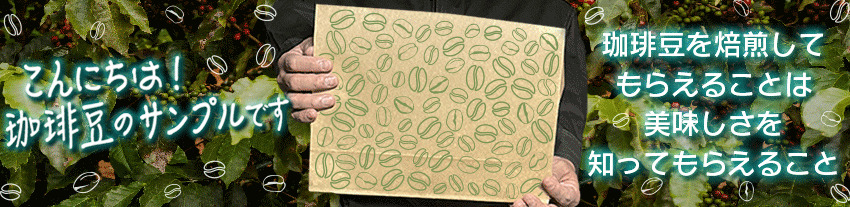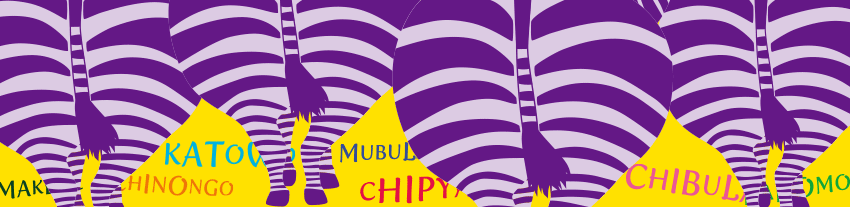2025/08/01
(NO.1746) 月夜の千本ノック デコッパチ
時々、なかなかやるせなくなると、日経新聞の「私の履歴書」を読み返す。最近では、早川書房の社長さんが書いており、小説家の村上春樹氏(ロング・グッドバイの翻訳について)やイシグロ・カズオ氏のエピソードがなかなか面白かった。
さて、2007年頃に長嶋茂雄さんも書いている。才能があふれ、運にも多少恵まれていたが、1954年に立大に入学した頃について書いたものを読むと、いろいろな先入観が遠くへ吹き飛んでいく。無数・有数のいろいろな人が、長嶋さんについて、いろいろなことを語っている。特集号的な雑誌も、思わず買ってしまった。しかし、書き手の思惑やフィルターが入り、どうも私(猫)の魂に訴えるもの、強く響くものは少ない。一方、ミスターご本人の書いたものは、すうっと染み込んでくるし、真実に相当近いと思う。西武池袋線の東長崎駅にあった立大のグラウンド。当時31歳の砂押監督のもとでの練習は、なかなか凄まじい。監督以外にも、コーチとして、先輩2人がついたという。時代がそのようなものだったのかもしれないが、私などは、読んだだけで卒倒しそうである。
一年生の長嶋選手は、当時の立大の遊撃手と比べて守備は劣っていたため、練習がなかなか終わらない。失策をすると、新人教育係から殴り倒される。殴られたことで、それでやり直すことが許される(なんてことだ・・・)。時には長嶋選手の代わりにコーチも殴られたらしい。夕暮れまで練習し、夕食後は、監督から呼び出され、夜間の守備練習。照明はなく、月明かりはあったかもしれないが、暗闇の底から、監督の声とゴロが飛んでくる。しかも、監督は、グラブで捕球しようとするな、心で捕れという。
エラーをすると、グラブを外せ、となる。しかし、次第に素手での取り方がわかってきたという、球際の処理に強くなって変化に対応できるようになったというのだから、再度たまげてしまう。
これを読み、大学野球の一、二年生のときが、ひとつの大きな節目であったことがわかった。プロ野球より人気が高く、観客数も数万人。外野左翼、右翼席への距離も今の神宮球場より10メートルほど長く、ホームランの難易度は高かったようだ。長嶋さんや大学野球についてわたしは、すこし誤解をしていた部分がすこし晴れたように思う。苛烈、過酷な練習をしたから、というよりは、これほど突き抜けた環境のご経験を読むと、あらためてうなるしかない。ちなみに、長嶋さんは大学の後、プロの球団として、南海か、巨人に入るかについて、たいそう悩んだそうだが、ヤクルト(国鉄スワローズ)という選択肢はなかったのだろうか。
2025年8月1日 デコッパチ
◆最近の ピリオドの向こう側
- 2025/12/08(NO.1789) スパルタ デコッパチ
- 2025/12/05(NO.1788) おなごの勘! 小濱綱之
- 2025/12/04(NO.1787) ゲイシャの味は産地による 岡 希太郎
- 2025/12/01(NO.1786) 自堕落に生きながらえて 山田雄正
- 2025/11/26(NO.1785) まともじゃない! 小濱綱之
- 2025/11/25(NO.1784) 遠い時代の人ばかり 山田雄正
- 2025/11/17(NO.1783) 若いふたり 山田雄正
- 2025/11/17(NO.1782) クマ騒動! 小濱綱之
- 2025/11/12(NO.1781) ぼくたちの「水俣」に出会う② 小山伸二
- 2025/11/10(NO.1780) 松茸ご飯でもしましょうか 山田雄正
>>リスト表示