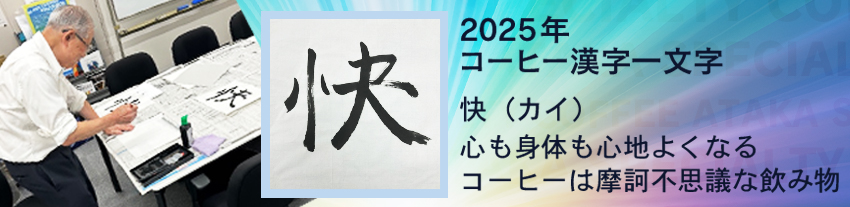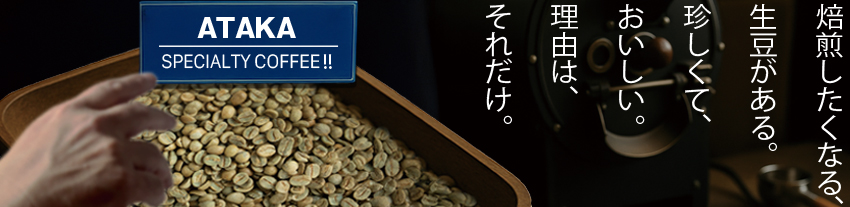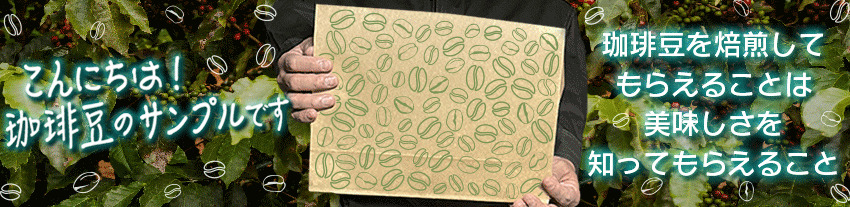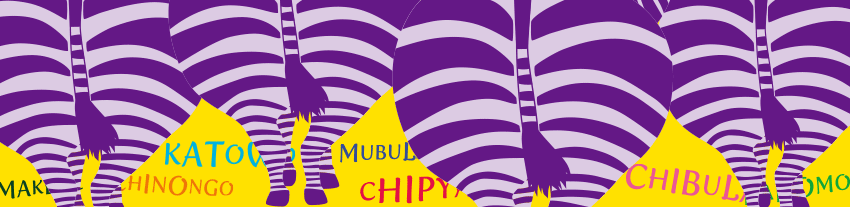2021/03/15
(NO.1258) 【コロコロほろ酔い日記-12】本を読もう ・・・ 小山伸二
春の嵐のように、風が強い日曜日。太陽が眩しくて、目を開けていられないくらいだ。
新型コロナ・ウィルスのおさまる気配のない3月もなかばを迎えている。
花粉が人類を苦しめているのは、いまに始まったことではないのかな。どうだろうか。
杉、檜。世界にアジャストできないぼくの鼻がぐずり、目がしょぼしょぼする。ぐじゅぐじゅで しょぼしょぼのまま、深煎りの珈琲を啜りながら、まあ、気を取り直して、本でも読むとしよう。
文字だけで構成されている紙が製本されているオブジェとしての本は、人類の発明のなかでもベス ト10に入るのではないだろうか。
というわけで、今年に入ってから紹介した本をここに置いておこう。
『夜のふたりの魂』ケント・ハルフ(河出書房新社)橋本あゆみ・訳 2018年 不思議な物語だ。高齢のふたりの物語。どちらもパートナーを亡くして久しい。いまは、独身者。
舞台はアメリカの田舎町。どんなに高齢になっても、人の目は気になる、そんな町だ。 そんななかで、ふたりの男女の不思議な関係がたんたんと、会話を中心に進行していく。さあ、 この物語、エンディングはどうなるんだろう。
読み進めていくと、最後にたどり着くのは。 人間は、かならず死ぬ。1回しかない、有限の時間のなかを、生きるだけ。 結末なんて、そうそう簡単にはわからない。それでも、生きている、ふたりの物語。 しみじみする。 ちなみにこの作品、Netflixオリジナルで『夜が明けるまで』という邦題で配信されている。ロ バート・レッドフォードとジェーン・フォンダ主演という形で(小説の世界観とは違う空気が支配 しているように思える)。
『本は読めないものだから心配するな』管啓次郎(左右社)新装版2011年 「あらゆる読書論の真実とは」、「本は読めないものだから心配するな」である、とこのユニー クな読書論、あるいは本を読むという行為に、ぼくたちを優しく誘ってくれるこの「1冊」は始 まる。 そもそも、「本」を「1冊」という、ひとかたまりのものとして、カウントすることを疑え、と この本は言う。どこから読んでも、数行読んでも、表紙や背表紙だけを読んでも、本と出会うこと になる、と。 精読、斜め読み、抜き読み、量も、質も、自由自在、自分のそのときの気分(あるいは、さしせ まった課題)にあわせて、臨機応変に、本とつきあえばいい。そんなふうにして、自由な読書の 実践を、この自由な本、まるごと1「冊」がぼくたちに教えてくれる。
こんな「先生」に、若いときに出会っていたらなあ、なんて。ぼくと同じ年の詩人のこの著作に 惚れました。
「迷う必要はない、きみは詩を読めばいい」。詩を読む人生は素晴らしい。
うん。 田村隆一センセイが「言葉なんかおぼえるんじやなかつた」なんて、かっこよく啖呵を切っている のも、詩のなかなんだから! 各見開き左ページ上に、昔の雑誌「ぴあ」の「はみだしぴあ」(わかる人にはわかる!)のよう に、あるいは章タイトルの「柱」みたいに1、2行のフレーズが抜き書きしてあるが、それを追い かけるだけでも楽しい。
まるで、本をめぐる旅に、著者と一緒に出かけているみたい。 Don’t Worry, Books are Unreadable Anyway
『今帰仁で泣く』水島英己(思潮社)2003年 沖縄の「今帰仁」。ナキジン。詩のなかで泣いているのは詩人ではなくて、言葉が泣いている。
そのとき「もはや」ない、「いまだ」ないもう一人のおまえも泣く
今帰仁で泣く
泣いた
水島英己の詩集のなかでも、いちばん、好きな詩集だ。
そこでは泣けない、泣かない、ぼくたちの今日に響く詩がぎっしりと詰まっている。
2021年3月14日 小山伸二
◆最近の ピリオドの向こう側
- 2025/12/25(NO.1794) 詐欺とクマ! 小濱綱之
- 2025/12/22(NO.1793) あなた死んでもいいですか 山田雄正
- 2025/12/17(NO.1792) なめたらいかんぜよ! 小濱綱之
- 2025/12/15(NO.1791) わが身の業も煮ゆるかな 山田雄正
- 2025/12/09(NO.1790) 生きている不思議 山田雄正
- 2025/12/08(NO.1789) スパルタ デコッパチ
- 2025/12/05(NO.1788) おなごの勘! 小濱綱之
- 2025/12/04(NO.1787) ゲイシャの味は産地による 岡 希太郎
- 2025/12/01(NO.1786) 自堕落に生きながらえて 山田雄正
- 2025/11/26(NO.1785) まともじゃない! 小濱綱之
>>リスト表示