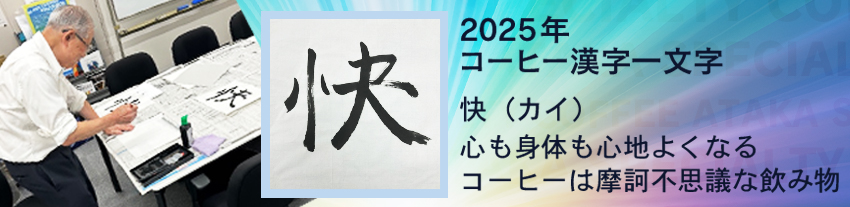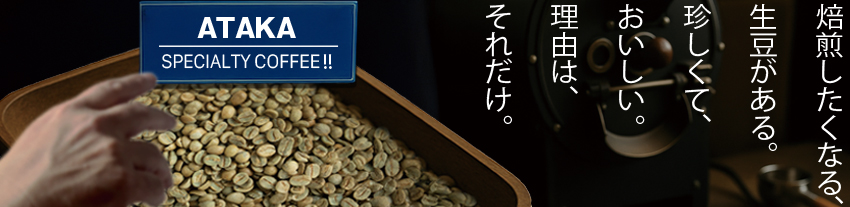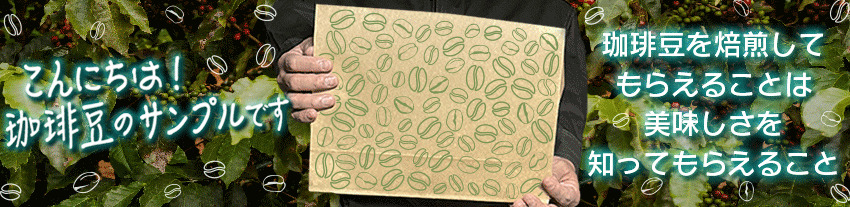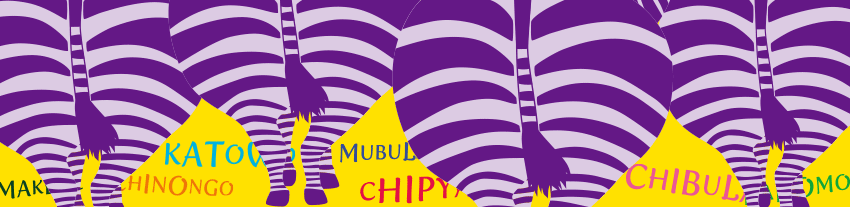2020/10/29
(NO.1235) 柴又帝釈天 デコッパチ
白洲次郎の奥さんである白洲正子の対談集などを読んでいたら、赤瀬川原平という作家との対談で、赤瀬川氏が脚本を書いた映画『利久』(1989年公開、主演 三國連太郎、山崎努)に触れている。この映画の監督である勅使河原宏氏は、美術感覚に溢れ、草月流家元でもあり、「砂の女」などを撮ったひとである。この映画(利久)は、映像や役者さんの動作、出てくる道具などがあまりに研ぎ澄まされている。こういう映画をみてしまうと、そのほかの映画の色彩がやや褪せてみえてしまうときがある。しかし、利久さんも、なにもそこまで意地を張らないで、ひとことあやまれば、あのような事態にならなかったのに。
恋い焦がれるように、この作品をもう一度みるために、草の根をかき分けるように(死語ですね)、探した。ようやく、某動画サイトの松竹映画サービスを契約すると視聴可能になることがわかり、少し松竹ワールドにお邪魔してみる。ついでに、ついつい、40作以上ある、男はつらいよ・シリーズにはまりこんでしまう。
わたしが20代のときは、実はあまり寅さんシリーズが好きではなかったが、30代半ばを過ぎた頃から、なんとなく憎めなくなる。最近では、魅入ってしまう。人情があつく、口上はアリアのように達者で、ある時は迫力をもってひとを説き伏せる。今回は、全作品の9割くらいをみる羽目になってしまった。どっぷりである。
ご存知の通り、毎回のパターンは、テキ屋稼業の寅さんが、旅先で夢から覚めて、ふらりと、生まれ故郷の葛飾柴又の草団子屋・本家とらや老舗(叔父夫婦が営む)に帰ってくる。たまに帰ると、食卓に自分のメロンがないとか(半年ぶりに急に帰ってきてもないのは当たり前である)、自分の部屋が貸家になったことなどに怒り、大喧嘩に至り、旅に戻る。または、美女に遭遇し、そのまま柴又に残ることもある。旅先や、柴又で惚れてしまったあとはご存知の通りである。
寅さんシリーズを一度見始めると、引き込まれるのはなぜだろうか。喜劇であること、妹さくらの存在、テンポのよさ、おいちゃんの嘆き、日本各地の山河の美しい絵、人情、寅さんがいない間のドタバタ、タコ社長との喧嘩、人間国宝みたいな芸術家に妙に気に入られる寅さん、時々ふいと出てくる疲れたサラリーマンたち、満男の成長、などなどであろう。
なんと、第17作では、一度はソ連に亡命し、一時帰国した名女優の岡田嘉子も出演している。第8作では、門前に喫茶店を始めた池内淳子にぞっこんになる。また、寅さんからの電話がしばらく途絶え、消息不明のときは、さくらが新聞に、訪ね人広告を出す場面もある。ネットも携帯もないのだ。
松竹映画は、人間を描く角度や距離が、東宝映画とかなり異なる気がする。なんともきめ細やかで、所作や口上ひとつひとつが繊細である。歌舞伎と関係の深い松竹が、小津安ニ郎や原節子をうみ、宝塚を母体とする東宝が、三船敏郎、加山雄三といった眉毛の濃ゆい人たちの映画群を作ることができた謎を、最近毎日考えている。
今回、もう一度み直してみると、寅さんは100%ふられていたわけではないことが再確認できた。
第44作では吉田日出子に言い寄られており、甥の満男が邪魔さえしなければ、旅館の主人になっていたかもしれない。32作ではお寺の住職の娘の竹下景子と、あと一言あれば、結婚していたのであろう。肝心な時になると、急いで逃げ出すのである。同作では、寺の住職助手を務めるなど、魚が水を得たような仕事ぶりを発揮することもある。
初期の第10作では八千草薫(幼馴染みの美容師)は、言葉の行き違いがあったもの、寅さんとの結婚を承諾する。しかし、寅さんは、照れて、はぐらかして、逃げる。微妙な会話のずれや誤解によって真実があらわになったのに、彼は逃げる。また、第45作では、宮崎県油津において、床屋さんを営む風吹ジュンに気に入られ、髪結の亭主になりかけていたのに、また逃げた。4回以上の作品に出てくる浅丘ルリ子(歌手のリリー役)とはかなりの相思相愛であったが、毎回けんか別れでおわる。
とらやという空間が、この映画の根幹である。帰るところがあるから旅暮らしができる。門前の老舗のお団子屋の叔父夫婦は、彼が店を継ぐことをいつも待っているのである。寅さんが何度か改心したときは、商店街の人たちも、今回こそは変わったのか?!と言い始めるのである(その度に裏切られる)。その気になれば、いつでも老舗の主人になれるのである。しかし、どうも一箇所に落ち着くことができない。団子をこねることも苦痛のようだ。
最近、わたしは、寅さんの叔父である、おいちゃん(車竜造)マニアになりつつある。おいちゃんは、喜劇出身の森川信(第1−8作)、ラグビー選手の経験のある松村達雄(9−13作)、民藝出身の下條正巳(14ー48作)の3人が演じた。
それぞれ、素晴らしい役者さんであることが、ようやくわかってきた。私は、何事も、気づくのが遅いのである。森川信のおいちゃんは、どこか抜けていて、いくばくか寅さんに巻き込まれがちである。寅さんが馬券で大当たりし、ハワイにいく事になり、数十人から盛大に見送られるが、詐欺のために航空券がない。夜中にこっそり、夫婦と寅さんが、とらやに帰る。その後、雨戸を閉め、電気をもらさず、近所に知られないように隠れ住むのは、戦後最大の喜劇である。
一方、ややくずれた学者先生の雰囲気を持つ松村達雄は、声がいい。ぼやき方も粋である。嘆き方もただものではない。三代目おいちゃんである下條正巳は、背筋がピリッとしており、お侍さんや家老などの雰囲気がある。山田監督は、「じっとしていらっしゃるだけで、そこにすでに存在感がある。演じなくてもいい。居ればいいという。それは究極の映画俳優の形ですよね」と語ったという。
もしも、映画「利久」において、秀吉役が山崎努でなく、森川さん(一代目おいちゃん)だったら、利久は秀吉と花見にでも行って仲直りしていたのではないか。もしも松村さん(二代目おいちゃん)だったら、取っ組み合いはしただろうが、和解したであろう。下條さん(三代目おいちゃん)が秀吉役だったら、利久はなんらかの責めを負いつつも、切腹は免れたのではないか。
2020年10月26日 デコッパチ
◆最近の ピリオドの向こう側
- 2025/12/22(NO.1793) あなた死んでもいいですか 山田雄正
- 2025/12/17(NO.1792) なめたらいかんぜよ! 小濱綱之
- 2025/12/15(NO.1791) わが身の業も煮ゆるかな 山田雄正
- 2025/12/09(NO.1790) 生きている不思議 山田雄正
- 2025/12/08(NO.1789) スパルタ デコッパチ
- 2025/12/05(NO.1788) おなごの勘! 小濱綱之
- 2025/12/04(NO.1787) ゲイシャの味は産地による 岡 希太郎
- 2025/12/01(NO.1786) 自堕落に生きながらえて 山田雄正
- 2025/11/26(NO.1785) まともじゃない! 小濱綱之
- 2025/11/25(NO.1784) 遠い時代の人ばかり 山田雄正
>>リスト表示