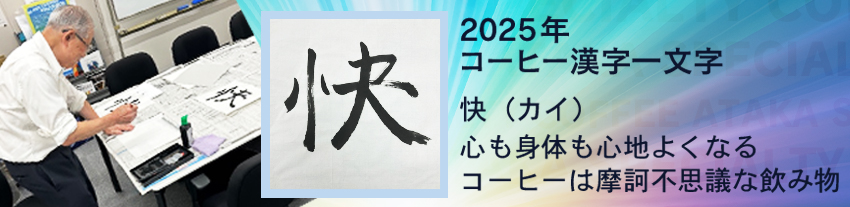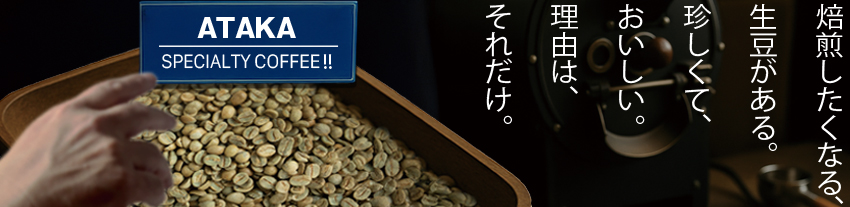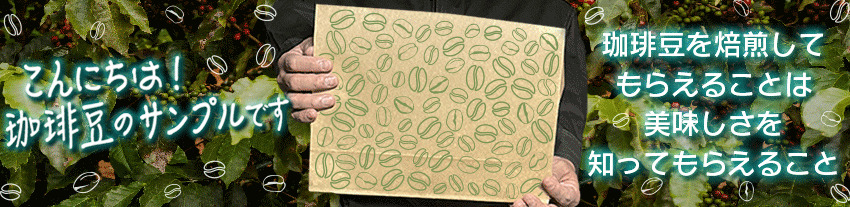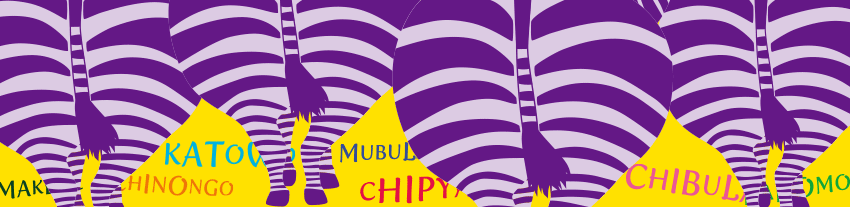2020/09/25
(NO.1231) 卵と壁 デコッパチ
作家・ムラカ・ミハルキの短編には、相当気をつけた方が良い。各短編のページ数は決してそれほど多くはないものの、一部の短編は、二時間程度の映画になるほどの奥行きや示唆を持ち、また、映画監督の一部が強く映画化を熱望するほどの何かを持つ。その何かは、読者のなかの、少なくない部分のひとびとに、どう控えめに見ても少なくないショックを与えてしまう。読者の心身のなかに、数年、十数年と、その驚きや、展開や文体が、居残り続けることになる。
私も、幾度か、いくつかのそのような短編に出会った、あるいは衝突してしまった。例えば、ハナレイ・ベイ、パン屋再襲撃、トニー滝田、加納クレタ、などなどである。もちろん、氏の短編のなかにも、印象に残りにくいもの、比較的静かに終わるもの、これは私には合わないなあ、なんだこれ?という短編もある。
しかし、氏の短編は、けっこうおもしろい。唖然とするしかない場合もある。ホラー的(柔らかなホラーもある)な展開になる場合は、映像にすると目を覆うよな場面でも、文章は極めて乾いており、一見して清潔感漂う文体に浄化?されたような気になる。または、たったの数行で、ひとりのジャズマンが、終戦直後の中国で、成り行きで戦犯捕虜になり、死にあと数ミリまで迫る状況が、さらりと描かれていたりする。あるいは、呪術的な空腹感を妻に告げたら、なぜかしら猟銃を保有していた彼女と、夜中にマクドナルドを襲撃するはめになる。
野暮で湿気のある文章でないために、ジャズの名演奏のように、そのときはいっきに最後まで読まされてしまう。または、不思議なほど、読んでいるときは重くない場合もあるが、知らぬ知らぬうちに、からだのなかで、撒かれた種子が膨らんでいく錯覚を植え付けられる。
とくに用心したい点は、短編である。たった数行で、異界、あるいは予想もしなかった展開にひきづりこまれることである。長編だったら、8時間くらいの演劇やオペラみたいに、舞台装置やストーリーの流れが大掛かりであるため、ふとした予兆を察知して、読者は、心理的衝撃が起きる前に逃げることも出来よう。しかし、短編はそうはいかないのである。
登場人物の奇妙な行動・発言あるいは、それに対する小説内の家族や同居人の反応は、まさしく、他の作家とは、発想が全く異なる。異界からふらりとくるのだ。他人からきいたらしい話の場合でも、闇みたいなものをさらりと描きだす。いわゆるムラカミワールドに連れて行かれるのだ。
三島由紀夫みたいな天才的な、立ち上がるような、挑んでくるような文章ではない。江藤淳や小林秀雄みたいな剃刀のような批評文でもない。ムラカミワールドという言葉を使いたくないが、しょうがないであろう。それしか思い当たらないのだ。
ムラカ・ミハルキ氏は、自分のことを、モーツァルトのような天才ではなく、岩を少しづつ穿って、削って、水脈をコツコツと探し、水脈に当たることもある、凡人だと評する。しかし、凡人がイスラエルから文学賞をもらえるであろうか。ひとが止めるのもかかわらず、現地で政権をやや批判するようなスピーチをするだろうか。
平易に見える文体で、あっという間に、アナザーワールドにつれていく文章。ストーリーは奇妙ですこしダイナミックでもある。または、同時代の地球人の、表層、深層をさらりとえぐる。時代が彼をつくったと仮定したら、戦後という時代もやっかいで複雑である。数十年に一度は出てくる類の作家であること、ゆえに、戦後が近代でもとくに異常な時代でないこと、を願いたい。
最近、ミハルキ氏は、数年ぶりに短編を出した。「一人称単数」。フィクションでないとしたら、氏の思春期時代からのエピソードと読めなくもないが、やはり、各編には、曲がり角や、曲がった後のささやかな衝撃が待っている(ヤクルト球団へのかなりの偏愛を綴った編を除いて)。過去の自分のことを小説にしたとしたら、少し寂しい点もある。しかし、現時点では氏の関心が、他者ではなく、ちょっと内面や青年時の過去に寄り道して、すこし掘り起こしたいものがあったのだろう。もちろん、こちら側も、掘り起こし作業にすこし参加できた。動画やSNSなど、ネットの海におぼれるのもよいが、出版業界に貢献するのもよいと思う。
2020年9月24日 デコッパチ
◆最近の ピリオドの向こう側
- 2025/12/25(NO.1794) 詐欺とクマ! 小濱綱之
- 2025/12/22(NO.1793) あなた死んでもいいですか 山田雄正
- 2025/12/17(NO.1792) なめたらいかんぜよ! 小濱綱之
- 2025/12/15(NO.1791) わが身の業も煮ゆるかな 山田雄正
- 2025/12/09(NO.1790) 生きている不思議 山田雄正
- 2025/12/08(NO.1789) スパルタ デコッパチ
- 2025/12/05(NO.1788) おなごの勘! 小濱綱之
- 2025/12/04(NO.1787) ゲイシャの味は産地による 岡 希太郎
- 2025/12/01(NO.1786) 自堕落に生きながらえて 山田雄正
- 2025/11/26(NO.1785) まともじゃない! 小濱綱之
>>リスト表示