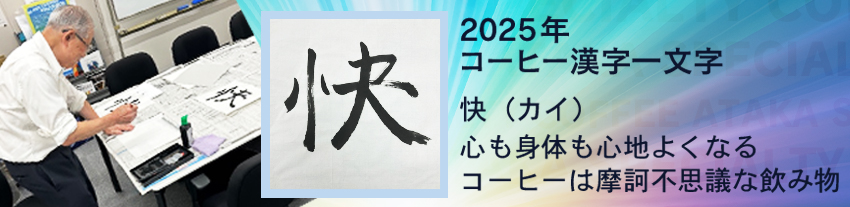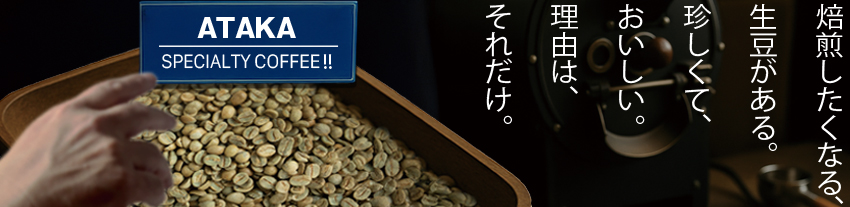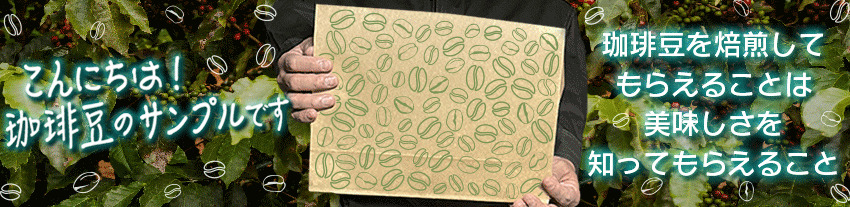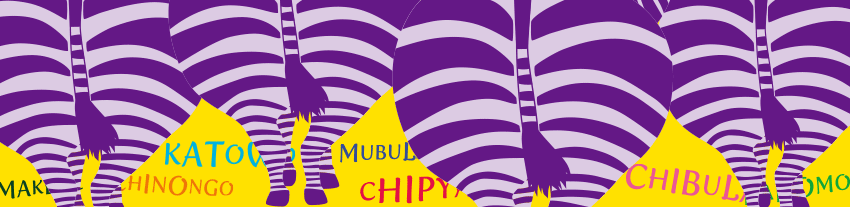2020/04/02
(NO.1210)【コロコロほろ酔い日記ー8】ステイホーム、今夜は眠れない 小山伸二
「多くの人が新型コロナウイルスの大流行をグローバル化のせいにし、この種の感染爆発が再び起こるのを防ぐためには、脱グローバル化するしかないと言う。壁を築き、移動を制限し、貿易を減らせ、と。だが、感染症を封じ込めるのに短期の隔離は不可欠だとはいえ、長期の孤立主義政策は経済の崩壊につながるだけで、真の感染症対策にはならない。むしろ、その正反対だ。感染症の大流行への本当の対抗手段は、分離ではなく協力なのだ。」
壮大な人類史を語って来たひとの言葉だ。
眠れない夜に、あえてコーヒーを飲んでネットの世界を検索してまわる。
ニューヨークで暮らす大阪の泉州出身の女性の動画にたどり着いた。
落語家・桂吉の丞さんの妹なんだそうだ。ちなみに、吉の丞さんは、ぼくの贔屓にしている桂吉坊さんの弟弟子さんだ。
で、その彼女の動画のタイトルは、「!ほんまに聞いてほしい!マジでコロナを舐めたらあかん」。
思わずひきこまれた。
リアルな語り。
大阪の泉州の語りは、そのまま文字起こししたら町田康の小説になりそう。
ニューヨークでシングルマザーやってる生活力というか、泉州弁で、ニューヨークのいまを、この状況下でコロナを生き抜いている、現在進行形の「語り」にひきこまれる。
冒頭に引用した世界的な大ベストセラー作家のユヴァル・ノア・ハラリさんの語り(翻訳は河出書房新社のベストセラー本と同じ柴田裕之さん)も、すっと入って来るし、立派だ。
その通り。
時間軸を、この惑星の時間とは言わずとも、わずかな歴史しか持たない人類、とりわけホモ・サピエンスの時間で眺めていても、いまこの地上でやれマスクが足りないとか、トイレットペーパーのことを気にする小さなぼくたちからみたら、十分に長い尺で物事、見てはるなぁと、さすがハラリさんやわぁ、ってなぜか関西弁で感心してしまうのだ。
さて、ニューヨーク。
ぼくの友人も住んでいて、ほんとうに心配だ。
コロナウィルスで亡くなった方々の遺体を安置する場所が圧倒的にたらずに保冷車が出動したり、街中に突然、遺体を安置するテント村ができたり。
わずか数週間のうちの出来事だった。
そして、ぼくの住んでいる東京はどうなるんだろう。
他人事なんかじゃない。
基本的に、だれもがすでに感染していてただ発症していないだけだ、と仮の前提に立ってみると、自分が感染するかしないかではなく、他人にうつさないためにどんな行動をとるべきか、となる。
基本的にみんなが、この仮の前提に立てば、おのずと極力、外出を控えるとか、マスクを他人のために可能な限りする(なければタオルでも巻くか!)。
そして、最終的には、可能な範囲内でステイ・ホーム、ということになるんだろうなあ、とぼんやり考える。
そうこうしているうちに、コーヒーだけではすまされなくなって、痛風を気にしながらも、ウイスキーについ手が伸びる、深夜2時すぎだ。
はい、ステイ・ホームです、いまは。
ハラリさんのお話は、河出書房新社のこちらのサイトで読めます。
http://web.kawade.co.jp/bungei/3455/
桂吉の丞さんの妹さんの動画はこちらで見られるはずです。
2020年4月2日 小山伸二
◆最近の ピリオドの向こう側
- 2026/01/05(NO.1795) どうなる2026年 山田雄正
- 2025/12/25(NO.1794) 詐欺とクマ! 小濱綱之
- 2025/12/22(NO.1793) あなた死んでもいいですか 山田雄正
- 2025/12/17(NO.1792) なめたらいかんぜよ! 小濱綱之
- 2025/12/15(NO.1791) わが身の業も煮ゆるかな 山田雄正
- 2025/12/09(NO.1790) 生きている不思議 山田雄正
- 2025/12/08(NO.1789) スパルタ デコッパチ
- 2025/12/05(NO.1788) おなごの勘! 小濱綱之
- 2025/12/04(NO.1787) ゲイシャの味は産地による 岡 希太郎
- 2025/12/01(NO.1786) 自堕落に生きながらえて 山田雄正
>>リスト表示