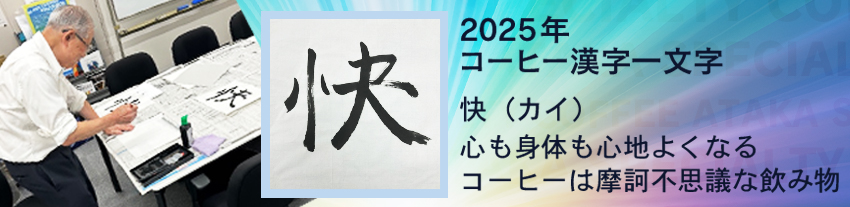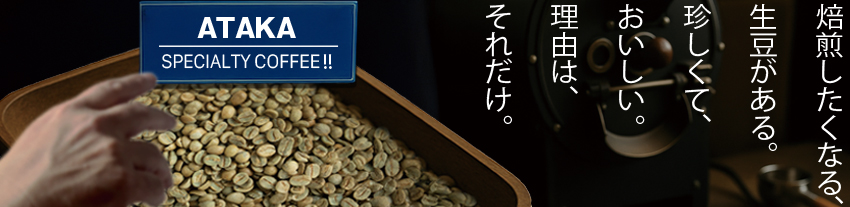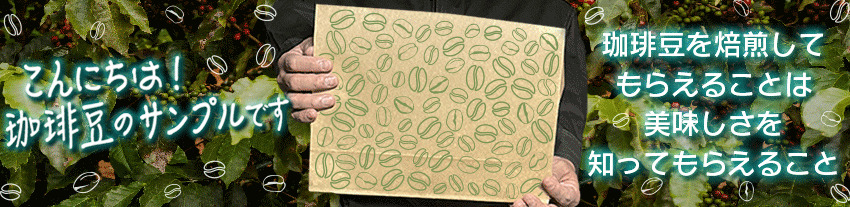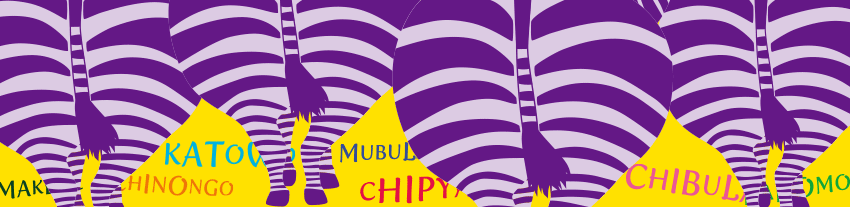2020/01/28
(NO.1200) 敵は遠野にあり デコッパチ
いま、勇壮な出だしで始まる、ショパンのピアノ協奏曲第1番ホ短調(「のだめカンタービレ」のノダメが国際的デビューを果たした曲)を聴きながら、司馬遼太郎の「国盗り物語」を思い出している。クラシックに造詣が浅い身であるが、雄大さと、大きな憂いを抱えながらの、繊細さは、この本と相通ずるものが少なからずあると思います。
斎藤道三。僧侶をやめて、京都の油売りのおかみさんを嫁さんにした男である。当時の油は、独占的な業者よる潤沢な産業であったこともあり、彼は、京における相当な富豪になったわけである。
なんと、それにもあきたらず、彼は美濃に赴く。僧侶出身ゆえの教養のたすけもあり、一家老に気に入られ、その後、当主の家に出入りするようになる。その後、かなりのすったもんだの末に、けっこう強引に、美濃一国の城主になる。詳しくは「国盗り物語」をお読みください。
その隣国は、勃興中で、経済基盤も豊かな織田家。美濃と、数回におよぶ激しい戦闘を繰り返す。やがて織田信長が、予想外に織田家の家督を継ぎ、和解機運のなか、斎藤道三の娘を嫁にもらう。織田信長も、道三も、あらゆる旧弊や経済不合理性、因習などを、本能的に嫌う性向があったようだ。相当に奇特な考えや思考を持つゆえに、かなり孤独であったと思われる信長に対し、道三は、意外にも、その後、手紙などで、浅はかならぬ教えを、信長に与えていったのではないかとみられる。間違えていたら、すみません。
一方、美濃の北方の武家であった明智光秀も、道三から、かなりの薫陶を受けた。二人は、ともに道三の愛弟子であったのだ。
明智光秀は、斎藤道三の娘(光秀の親戚でもある)にひそかに想いを寄せていたが、彼女を信長にとられ、しかも、その後、明智家が、いったん零落したため、浪人の身になってしまう。信長と境遇が違いすぎるではないか。
ながいながい不遇のときを過ごす。ときに、朝倉家のもとで陣を借りて戦をしたり、京都では、後に将軍になる足利義昭を、盟友とともに危機から救い、将軍にたてる。そのときの緊迫感や描写は司馬遼太郎の多くの本のなかでも、もっともスリリングな場面のひとつである。
その後は、ご存知の通りである。いろいろな謎が多いため、某国営放送の大河ドラマの脚本も、人々の定説を覆すような、常識をひっくり返すような、司馬史観とはまったく異なる結末にする、遊び心を持つ余白は大きいのではないかと思う。
いずれにしても、明智光秀は、当分、いろいろなライバルに仕えたり、争ったりしなければならない。加えて、視聴率的には、某民放が比較的成功させた、山のなかの一軒家(まれに海岸)的番組とも戦わなくてはならない。山や森林は、日本の国土の多くを占め、水をはじめ多大な恩典を都市に与える。同番組は日本の民俗学と無縁ではない。
遠野物語を著した民俗学者、柳田國男は語る。「思うに遠野郷にはこの類の物語なお数百件あるならん。我々はより多くを聞かんことを切望す。国内の山村にして遠野よりさらに物深き所にはまた無数の山神山人の伝説あるべし。願わくはこれを語りて平地人を戦慄せしめよ。この書のごときは陳勝呉広のみ。」(柳田国男「遠野物語」より)
明智光秀の敵は柳田国男なのです。
2020年1月23日 デコッパチ
◆最近の ピリオドの向こう側
- 2026/02/04(NO.1805) コーヒーは心臓病にも効く! 岡 希太郎
- 2026/02/02(NO.1804) 偶然・必然・当然 山田雄正
- 2026/02/02(NO.1803) 争点、焦点 デコッパチ
- 2026/01/26(NO.1802) 本なんか読まない 山田雄正
- 2026/01/20(NO.1801) 身の丈に合ったスタジアム! 小濱綱之
- 2026/01/19(NO.1800) いつも間違いそして今 山田雄正
- 2026/01/13(NO.1799) 強い奴を倒せ 山田雄正
- 2026/01/13(NO.1798) 詮無いこと! 小濱綱之
- 2026/01/09(NO.1797) 晩餐会、ワイン、コーヒー デコッパチ
- 2026/01/06(NO.1796) コーヒーノキの起源 岡 希太郎
>>リスト表示