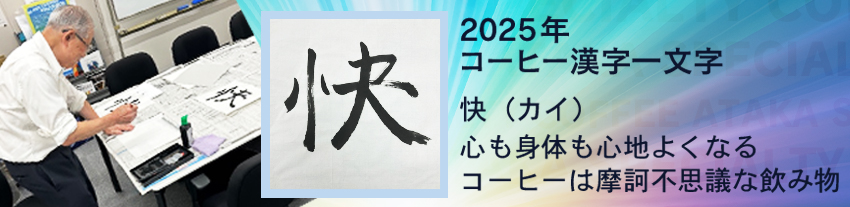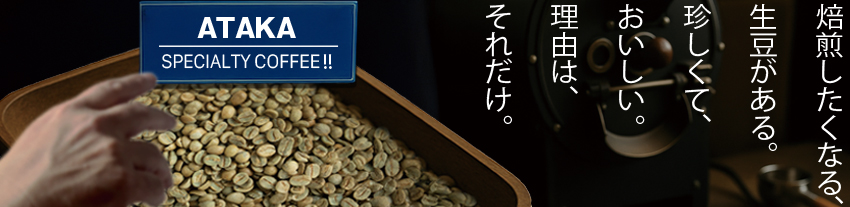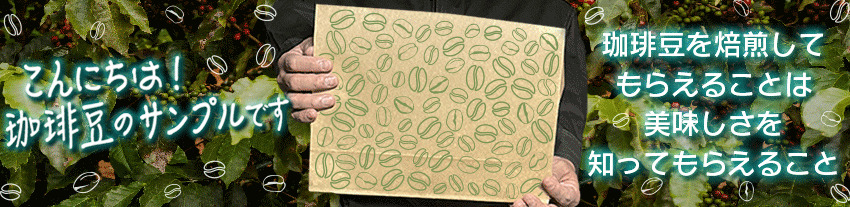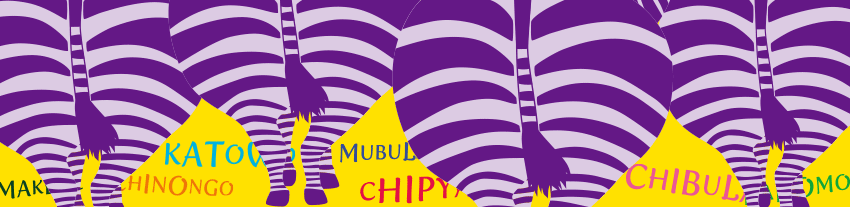2019/09/03
(NO.1181) コーヒーゼリーよ デコッパチ
最近、個人のかたが営むカフェで、感じの良いところが、近所にふたつほど見つかった。お酒をあまり飲めるほうではない身にとって、静かに落ち着いて、コーヒーに触れる場所が増えるというのは、たいへんありがたいことである。心の底からしみじみと思う。あきらめないでよかった。人生が、こころなしか、豊かになったような気がする。
「男、三界に住処なし」という言葉がある。このばかみたいに広い首都圏において、ゆっくりできる居場所がひとつ、ふたつ、増えても、ばちは当たらないと思う。遠泳において、ひと休みできる浮きブイのような。とりが羽根を休める止まり木の如く。
ひとつは、とある五差路の角に、いつのまにか、こじんまりと開店していた。入口付近に、以前、コーヒーゼリーがあります、という張り紙をみた残像記憶があったが、外部に向けた黒板的メニューは、すごく控えめであり、カフェなのかどうか、よくわからなかった。江戸切子(きりこ)を連想させるガラスで二面が覆われている。どうやらカフェみたいだ。とりあえず、勇気を出してはいってみると、想像していたものに近いコーヒーゼリーが出てきた。その後、結局、何度も、足を運ぶことになる。毎回、コーヒーゼリーとコーヒー、あるいは、ときどき、プラス・トースト。外からは、自然光がひかえめがちに、しずしずとストレートに入ってくる。
コーヒーゼリー。夏を乗り切りために存在するような恵みである。夏を乗り切るための盟友。コーヒーゼリーのコーヒーゼリーによるコーヒーゼリーのための小さな革命と句読点。プリンほどしつこくなく、漆黒な風貌が示すハードボイルドなクールさ。コーヒーだけがもつ、コーヒーの核心を、遠慮がちに、静かに提供してくれる。
一方、もうひとつのお店は、なかなか入るまでに時間がかかった。なかが全くみえない厚い木のとびらが入り口。小さな看板には、コーヒーという文字が浮かんでいる。宮沢賢治の、注文の多い料理店が、霧の彼方から連想される。とびきり頑固そうなマスターが経営し、音ひとつたててはいけなさそうな門構えだ。
しかし、二週間前に、身も世もない過酷な暑さを凌ぐために、入ってみた。理想に近い空間であった。これは現実なのかしら。ほんとうに2019年8月なのであろうか。暗めの空間に、バロック音楽、30枚くらいのレコード。富士山麓の氷穴を思わせる薄暗さ。若いマスターは、あまりに美味しい各種コーヒーをつくってくれる。どうやら幻ではないようだ。若い人の支持も徐々に増えているようだ。よきお店が差し出すコーヒーは、一種の静寂であり、美であり、たましいのよきありかた、なのでしょうか。
2019年9月3日 デコッパチ
◆最近の ピリオドの向こう側
- 2025/12/25(NO.1794) 詐欺とクマ! 小濱綱之
- 2025/12/22(NO.1793) あなた死んでもいいですか 山田雄正
- 2025/12/17(NO.1792) なめたらいかんぜよ! 小濱綱之
- 2025/12/15(NO.1791) わが身の業も煮ゆるかな 山田雄正
- 2025/12/09(NO.1790) 生きている不思議 山田雄正
- 2025/12/08(NO.1789) スパルタ デコッパチ
- 2025/12/05(NO.1788) おなごの勘! 小濱綱之
- 2025/12/04(NO.1787) ゲイシャの味は産地による 岡 希太郎
- 2025/12/01(NO.1786) 自堕落に生きながらえて 山田雄正
- 2025/11/26(NO.1785) まともじゃない! 小濱綱之
>>リスト表示