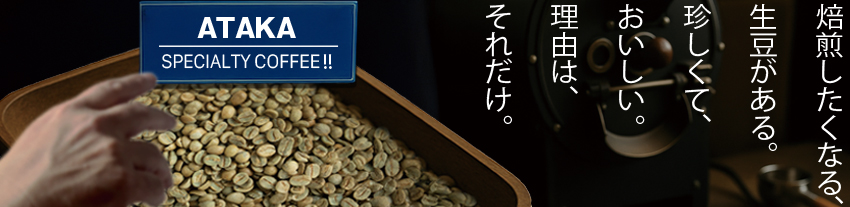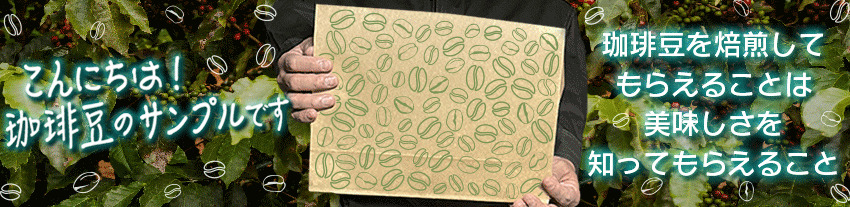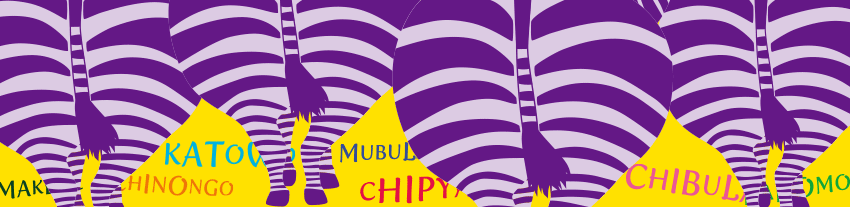2019/04/16
(NO.1156) 希望のかなた Decoppachi
希望のかなた、という映画をみました。THE OTHER SIDE OF HOPE.
夜のフィンランドの港。石炭か鉄鉱石を運ぶ船が入ってくる。クレーンがまっくろな鉄鉱石を、貨車におとしていく。
すこし、時を置いたあと、その黒い山で、動物が、モグラのように表面を揺らす。まずは頭らしき物体がでて、次に真っ黒な動物のひたいが。そして顔らしきものがあらわられる。そして目らしきものが開く。黒だけの世界に、白い色彩が現れる。人間ではないか。
やがて全身があらわれ、船内を歩き出す。まるで、ウルトラQの海獣ラゴン、地獄の黙示録のウィラード大尉、である。これだけで、彼、カーリドの中東からの過酷な過程が示唆される。米国あるいはロシア、あるいはISによって、家を爆撃され、婚約者も失い、行方が途絶えた妹を探しにヘルシンキに流れついたのだ。
勝手ながら、ここ数年みた映像のなかで、一番パンチのあるショットとなった。
彼、カーリドは、その足でまず、駅に向かう。有料シャワー室と警察の場所を駅員にきく。駅員は当然のように答える。
駅に、有料シャワー室があることに、わたしはまずは驚いた。彼は、体を洗い、警察に向かい、難民申請する。これも、当然のような流れ。彼はとりあえず収容施設に入る。
監督は、アキ・カウリスマキ。醸し出される、まじめな、とぼけたような雰囲気。米国映画の対極的位置。仏英映画とも明確な一線を画す、泥臭いけどソリッドな匂いがする。日本映画、米国映画、なにもかも、もういいや、と感じたときにみると、すっと入り込んでくる。言葉と言葉のあいだの無音で会話してるようにもみえる。しかしながら、このフィンランドという国は、内戦を経験したり、第2次大戦時のドイツ、ソ連、スウェーデンなどに対する複雑な立ち回り、終戦直前の戦争の駆け引きなど、大国に囲まれた現実への対処が上手い国だ。
希望のかなた。
ふたりの人物を同時並行にえがき、やがて邂逅するシナリオは見事だと思う。
もうひとりは、仕事を変えるフィンランド人の大柄の中年・初老男性、ヴィクストロム。ワイシャツの大量在庫を売り払い、奥さんといったんわかれ、レストラン経営を始める。さびれたレストラン。うらがなしい従業員3人付きである。
難民申請を、フィンランド当局から拒否されて、途方にくれ、駐車場で寝ていた、シリア人カーリドと殴り合いの喧嘩するが、不思議にも彼を雇いいれ、かくまったりする。
重い境遇なのに、どこかすっとぼけた映画である。敗者三部作で有名?な監督だが、これは、なんと呼んだらいい映画なのだろうか。希望一部作あるいは、難民三部作だろう。邦題が、希望のかなた。いい題名である。荒削りだけど、救いを求める人間と、北欧的な無骨でがっちりした善意がぶつかり合う。
ひとは、たまに、1年に一度、あるいは10年に一度くらい、純粋で貴重な進言、警告、金言をくれる。それに対して、照れないで、がっちり対応、行動、返答するべきである。わたしの頑固者の友人は、ときに偏屈かもしれないが、重要な岐路で、それらを受け止め、実としてきた。わたしは、見逃したり、見送り三振したりした記憶が少なくない。
わたしのかなたに、希望があるかわからないが、めさきの希望、課題をつくり、こわしたり、よけたり、たおれたり、しのいで、やっと、これを書けている。うなぎの寝床のようなカフェ。狭いところだが、世界の果てであり、週の末期でもあり、ほのかな喜びの世界の始まりでもある。不思議に安心できる場所で書いている。
2019年4月16日 Decoppachi
◆最近の ピリオドの向こう側
- 2025/07/11(NO.1740) 正直者は救われないのか? 小濱綱之
- 2025/07/07(NO.1739) 意味のない話 山田雄正
- 2025/07/04(NO.1738) 夏になると 小山伸二
- 2025/07/02(NO.1737) タウリン、お前は一体何者だ⁉ 岡 希太郎
- 2025/07/01(NO.1736) Feeling good デコッパチ
- 2025/06/30(NO.1735) 不変なものは不変 山田雄正
- 2025/06/27(NO.1734) 信じる者は救われる? 小濱綱之
- 2025/06/23(NO.1733) 何よりのご褒美 山田雄正
- 2025/06/16(NO.1732) 天国で野球を! 小濱綱之
- 2025/06/16(NO.1731) 三種の神器を生きる 山田雄正
>>リスト表示