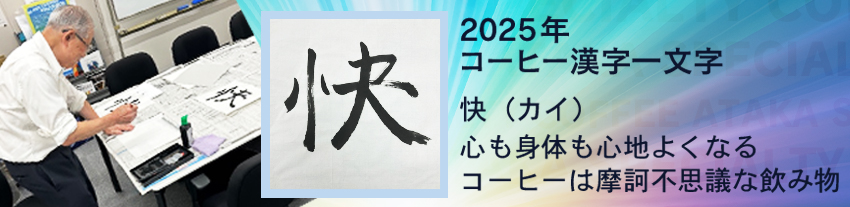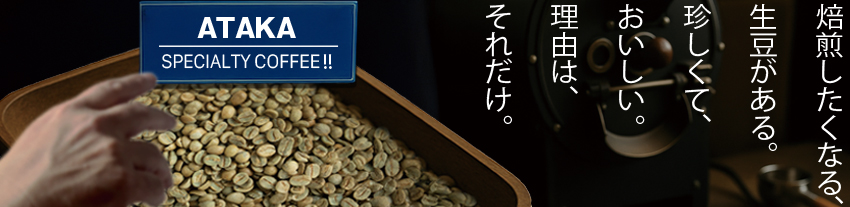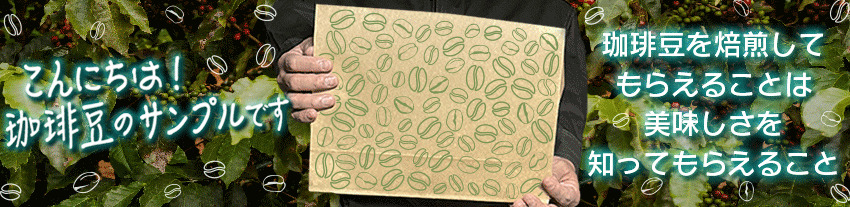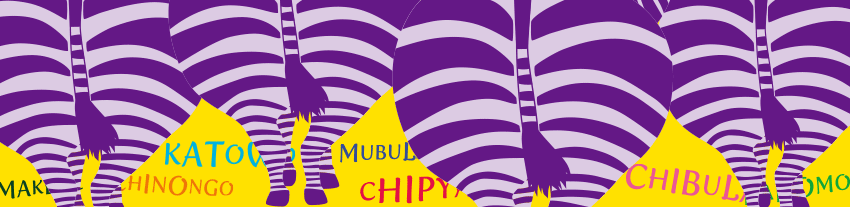2019/03/25
(NO.1152) みかづき Decoppachi
あまりテレビドラマにハマる方ではないが、はからずも、「みかづき」というドラマにはまってしまった。天才的な塾講師の旦那と、カリスマ経営者の妻、その母、子供や孫をめぐる物語です。二人で始めた塾が、大規模な企業になっていく過程の紆余曲折、大規模登山。
あるいは、ひとりの男、大島吾郎が、三人の女(大島千秋(旧姓、赤坂)その娘、千秋の母)に絡めとられた話でもある。
あるいは、小学校の用務員室にいた男が、伝説の塾講師になるはなし。
あるいは、エネルギーの塊みたいな千秋が、吾郎をとらえ、塾をふたりではじめる話。次第に、千秋は、教えることよりも、経営に目覚め、組織は巨大化していく。果ては、私立の学校設立を目指す。
千秋は凄い女性だ。竜巻のように吾郎をまきとり、ブルドーザーのように塾経営を軌道にのせ、同業者、世間と戦っていく。
あるいは、三人の娘がいた場合、三人が全く違う方向に進むという、よくある話。しかし、その過程が、たまらなくおもしろい。長女は母親のモーレツな反対を押し切り、公立高校の先生になる。次女は塾経営のミニブルドーザーをえらぶが、大きな失敗に出会ってしまう。三女はNPOの道に。
あるいは、戦後、いかに塾産業が立ち上がり、巨大化し、成熟期に至ったかのはなし。最初、世間や学校制度からの目は相当厳しく、文部省との対立も激しかった。
すぐれたビジネス書でもあろうが、わたしは、なによりも、大島吾郎の人柄、リズムに救われる。
原作本も読んでしまった。物語のなかで、何人もの男が、大島吾郎に共感し、共鳴し、惚れ込んで、吾郎とともに、塾教師になる。しかし、吾郎は、塾が、月のように子どもを柔らかに照らす路線から、受験志向の拡大路線に舵を切った直後に、去ってしまう。塾から大島吾郎が去ったあと、彼らは苦しむ。
テレビでは、吾郎は数年で戻ってくるが、原作は二十年の時を隔てる。テレビは体裁を考慮した編集映像あるいは宝石箱だとしたら、原作という存在は生豆、中身の宝石みたいなものか?しかし、映像における吾郎役の俳優さんにはまってしまう。映像のチカラもおそるべし。
もし、いま、働いていることに、疑問を持って、転職を考えているひとが、いたとしたら、まずは、先輩などのなかに、尊敬できるひと、共感できるひとが、いるかどうかを考えてほしい。
もしひとりでもいたら、今の職場に残った方がいいのではないでしょうか。尊敬すべきひとが、もし、ひとりもいなかったら、然るべき友人に相談すべきであろう。それでも気が変わらなかったら、若くして夭折した中島敦の「李陵」(短編です)、あるいはこの「みかづき」を読んでほしい。それでも、どうしてもということならば、お酒もよいでしょうが、とてつもない濃いコーヒーを飲んで、月を見上げてみましょう。
2019年3月24日 Decoppach
◆最近の ピリオドの向こう側
- 2025/12/22(NO.1793) あなた死んでもいいですか 山田雄正
- 2025/12/17(NO.1792) なめたらいかんぜよ! 小濱綱之
- 2025/12/15(NO.1791) わが身の業も煮ゆるかな 山田雄正
- 2025/12/09(NO.1790) 生きている不思議 山田雄正
- 2025/12/08(NO.1789) スパルタ デコッパチ
- 2025/12/05(NO.1788) おなごの勘! 小濱綱之
- 2025/12/04(NO.1787) ゲイシャの味は産地による 岡 希太郎
- 2025/12/01(NO.1786) 自堕落に生きながらえて 山田雄正
- 2025/11/26(NO.1785) まともじゃない! 小濱綱之
- 2025/11/25(NO.1784) 遠い時代の人ばかり 山田雄正
>>リスト表示