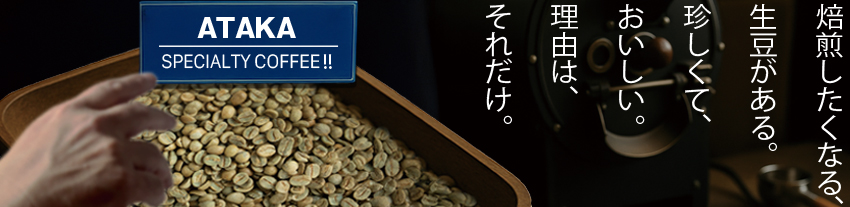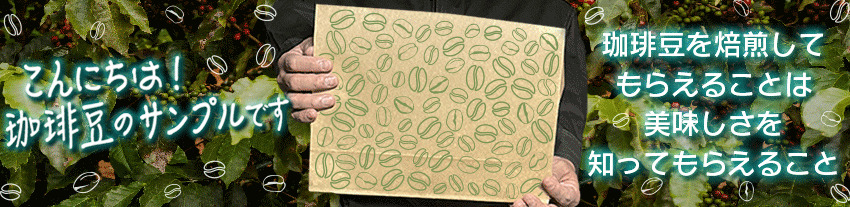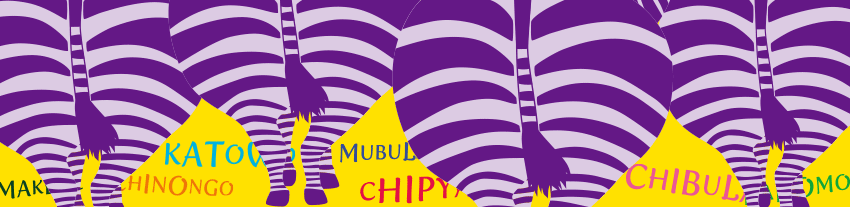Alishan Typica
阿里山(アリサン)ティピカ
-
 10Kg/
入荷4袋
·残0.0袋
10Kg/
入荷4袋
·残0.0袋
◆商品説明
日本統治の1930年代、日本政府は台湾に農業政策の一環としてコーヒー栽培を始めた。かつては昭和天皇献上品でもあった?台湾珈琲。復活です。
台湾コーヒーは、植民地農業の一環として、大日本帝国領土内で行われていた「国産コーヒー」です。日本が日清・日露・第一次世界大戦で勝利をおさめ、大日本帝国の領土が東アジアへと拡大するなか、日本人主義によるコーヒー栽培が行なわれ始めたのです。
台湾でコーヒーの栽培が始まったのは、1885年頃の清朝の時代でした。イギリス商人によって始められました。その後、清人によって台湾各地でコーヒー栽培は継続されますが、本格的な栽培が始まるのは、日清戦争後の1895年に締結された馬間条約による台湾割譲後でした。台湾総督府の農業技官であった田代安定は、コーヒー栽培は台湾の気候に適しているため、将来は内地輸出用の商品作物にしたいという意気込みを報告書で述べています。
1897年から台湾総督府中央研究所農学部を中心として、日本人による試験的コーヒー栽培が行なわれ、1912年までに産地の異なるコーヒーノキ(台湾系、小笠原系、ハワイ系、ブラジル系)が植えられていました。アラビカ種を中心にリベリカ種、カナリエ種、ローリフォーリエ種などの多品種のコーヒーノキが栽培することによって、積極的にコーヒー生産の可能性を模索していた時代でした。
1920年代に入ると、コーヒーノキは、試験場から花蓮港豊田村や吉野村などの移民開拓村にも移植され栽培され、台湾から日本内地への出荷が有望視されるようになりました。1930年代初期には、内地企業の進出によって、台湾コーヒーの大量生産が始められました。住田物産(現エムシーフーズ)が住田農場、木村コーヒー店(現キーコーヒー)が台東農場、嘉義農場を開き、栽培・収穫・販売まで全て会社が行なう直接経営方式が採られました。住田物産は1934年に初荷として70袋を大阪へ出荷しています。
台湾産コーヒーの有望な将来性を期待されたものの、労働者不足、天災・病害などのコーヒーノキの被害により、積極的にコーヒーを生産する農家がいないという問題に直面。さらに太平洋戦争の勃発によって台湾におけるコーヒー生産は終焉を迎えたのでした。
◆SPEC
| 品名 | 阿里山 |
| 生産国 | 台湾 |
| 地域 | 嘉義県阿里山 |
| 生産者 | Zhou Zhu Yuan |
| クロップ | 2011 |
| 規格 | |
| 欠点規格 | |
| スクリーン | スクリーン16アップ |
| 木の品種 | ティピカ |
| その他 | 標高1,200-1,300メートル、農園面積2ヘクタール、1996年から栽培 |
| 精製方法 | フルウォッシュド |
| 開花時期 | |
| 収穫時期 | 2011年4月 |
| 船積時期 | 2011年12月空輸 |
| 保管方法 | 事務所にて保管 |
| ロットナンバー |
- 1)商品・生産地の情報を不明な点も隠さず公開いたします
- 2)カップ品質でロットを選び取っていますので商品名の後にロット番号の最終末尾を明記しています。例)CAMPO ALEGRE1436
- 3)日本に入荷した時期や保管方法も開示いたします
各種マークの説明:
 単一農園:限定された農園・生産者が明らかな商品:
単一農園:限定された農園・生産者が明らかな商品: 地域限定:産出する農協限定など生産地域が限定された商品:
地域限定:産出する農協限定など生産地域が限定された商品: 天日乾燥:乾燥工程で手間暇かけた天日乾燥の原料を使用した商品:
天日乾燥:乾燥工程で手間暇かけた天日乾燥の原料を使用した商品: 原種豆限定:コーヒーの木の原種のみを厳選した商品:
原種豆限定:コーヒーの木の原種のみを厳選した商品: 品質認証済み:スペシャリティー協会・有機栽培など第3者による品質証明書付き、または準ずる商品:
品質認証済み:スペシャリティー協会・有機栽培など第3者による品質証明書付き、または準ずる商品: オークション・品評会入賞品:品評会入賞品:ネットオークション・各種品質コンテスト入賞商品:
オークション・品評会入賞品:品評会入賞品:ネットオークション・各種品質コンテスト入賞商品: サステイナブル・コーヒー:有機・環境・公正貿易の観点に配慮した地球と人にやさしい珈琲:
サステイナブル・コーヒー:有機・環境・公正貿易の観点に配慮した地球と人にやさしい珈琲: