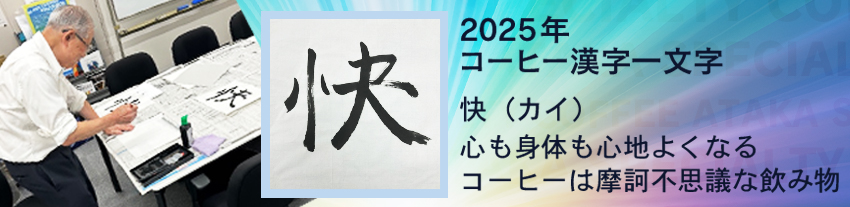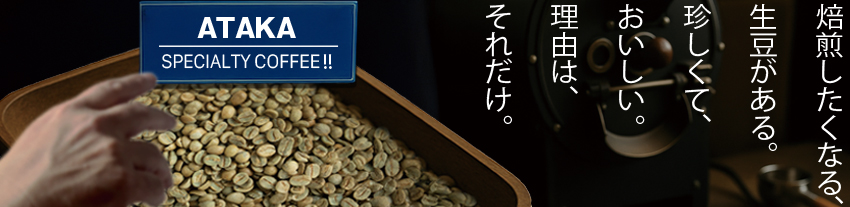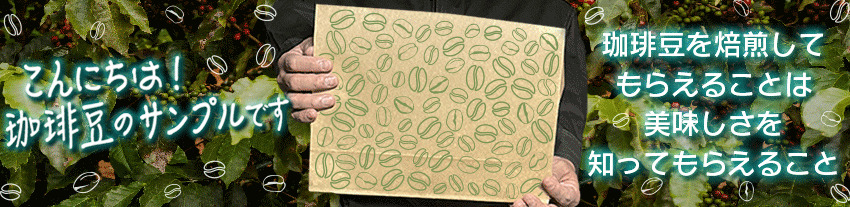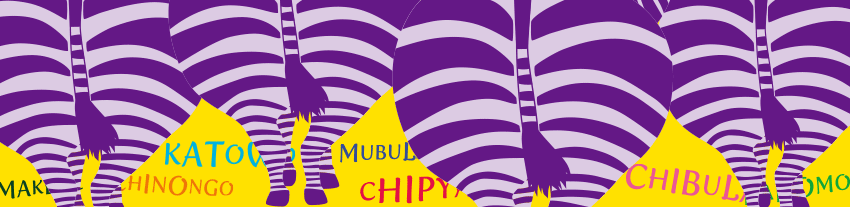2019/01/11
(NO.1139) 薬食同源 岡 希太郎
先日、NHK番組「あさイチ」で「薬食同源」をやっていました。中国古代の用語と言ってましたが、違います。番組では触れていませんが「医食同源」も中国生まれではありません。どちらも高度成長期の和製熟語なのです。新宿クッキングアカデミー校長の新居裕久氏が、「今日の料理(1972年9月)」で、ほぼ無意識に発した新造語が後に流行語になりました。今なら大賞です。
古代中国には四文字熟語こそなかったものの、食思想としての「薬食同源」が実在していました。その歴史を文献に従って忠実に解説したのは、茨城大学名誉教授・真柳誠氏です。読んでみたい方は「医食同源の思想-成立と展開」をネット検索してください。ここではかいつまんで紹介します。
古代中国には4種類の医者がいたそうです。その筆頭は「食医」と呼んで、王様の食事を調理するとき「春に酸を多く、夏に苦を多く、秋に辛を多く、冬に鹹を多く、そして調えるのに甘滑を用いる」、つまり五味を重視したそうです。王様が病気知らずに健康に長生きするための工夫であったと思われます。
「食医」に次ぐのは「疾医」と呼んで、現在の内科医のこと。特徴は「五味、五穀、五薬をもって病を養う」と書かれています。3番目は「傷医」と呼んで現在の外科医。特徴は病に対して「五毒を以って攻め、五気を以って養い、五薬を以って療し、五味を以ってこれを節す」とあり、やはり仕上げは五味なのです。五味を使わないのは4番目の獣医だけです。
と言いましても現代人にとって毎日々々五味を選ぶなど簡単ではありません。そこで古代養生訓を現代風に「五味五色」と表現したのはイタリア料理人でTVシェフだった某さん(名は忘れました)でした。何ともいい語感ではありませんか。消費者は五色の野菜を見た目で選べばよいのです。その結果どうなるかと言えば、病気予防のビタミンとミネラルがくまなく食べられるようになるのです。
薬食同源の実践法は、入門も卒業も「五味五色」、どうです、簡単でしょ!
2019年1月10日 岡 希太郎
◆最近の ピリオドの向こう側
- 2025/12/25(NO.1794) 詐欺とクマ! 小濱綱之
- 2025/12/22(NO.1793) あなた死んでもいいですか 山田雄正
- 2025/12/17(NO.1792) なめたらいかんぜよ! 小濱綱之
- 2025/12/15(NO.1791) わが身の業も煮ゆるかな 山田雄正
- 2025/12/09(NO.1790) 生きている不思議 山田雄正
- 2025/12/08(NO.1789) スパルタ デコッパチ
- 2025/12/05(NO.1788) おなごの勘! 小濱綱之
- 2025/12/04(NO.1787) ゲイシャの味は産地による 岡 希太郎
- 2025/12/01(NO.1786) 自堕落に生きながらえて 山田雄正
- 2025/11/26(NO.1785) まともじゃない! 小濱綱之
>>リスト表示