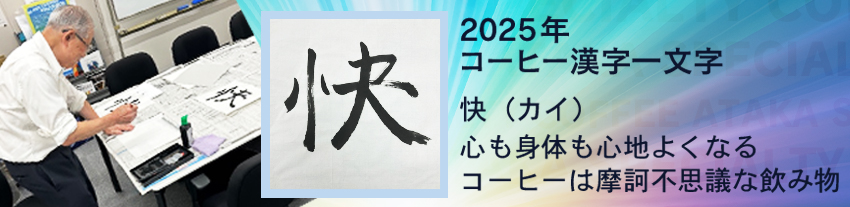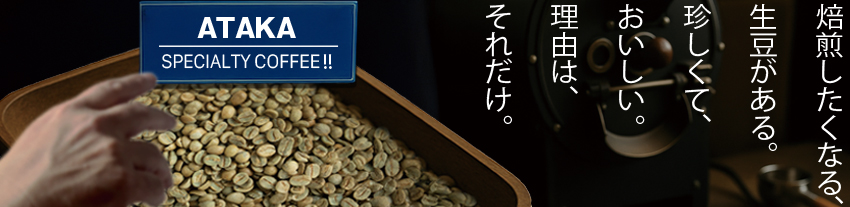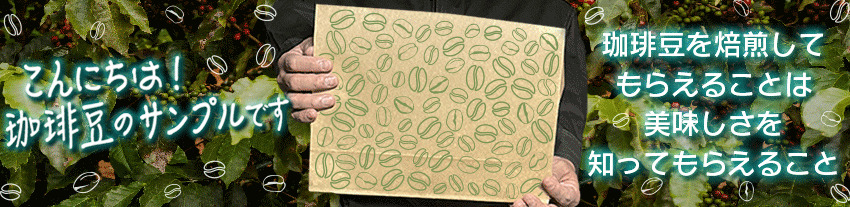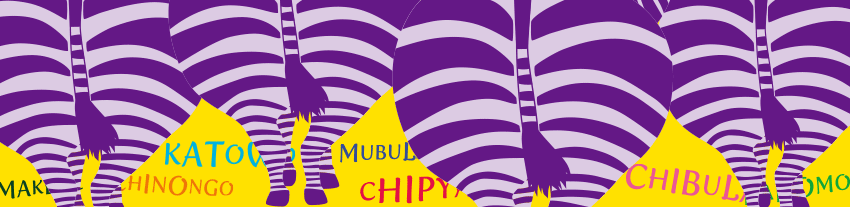2018/12/07
(NO.1135) 藩士の珈琲 岡 希太郎
去る12月2日の日曜日、日本コーヒー文化学会年次集会が開催されました。そこで弘前市の珈琲店主・成田専蔵氏が第1回学会賞を受賞しました。氏の功績は「珈琲で弘前の地域起こし」…弘前市の産官学を取りまとめ、「珈琲の街ひろさき」とのお題目を観光案内の目玉に育てたことです。氏が使う神器の1つ「藩士の珈琲」が抜群です。
「藩士の珈琲」には史実に基づく謂れがあります。その昔、コーヒー豆が日本列島に上陸するより前、津軽平野の農閑期の農民を幕府が召集し、オホーツク沿岸の露寇警備に派遣したのです。知床の斜里町では、一冬の越冬で100人のうち実に70人が浮腫病で亡くなりました。その時の慰霊の碑が残っています。
50年後、オランダ船が運んできたコーヒー豆に、浮腫病を予防する功徳があると説いたのは、長崎に居たシーボルトでした。曰く「日本人は薬としてのコーヒーがよく効く体質だからもっもっと飲むべきである」。それを聞いてか、蘭医はもとより漢方医までがコーヒーを勧めるようになったそうです。やがてそれを聞き付けた幕府は、津軽農民の次なる出兵で、宗谷岬にコーヒー豆を届け、毎日飲むように淹れ方と飲み方を指導したそうです。その冬、津軽藩兵に死人は一人も出ませんでした。
成田専蔵氏がこの史実に触れたのは、珈琲店を始めて間もなく、客の来ない店を家人に任せて、自らはコーヒーを学ぶ旅に出たときのことでした。最初に赴いた地が稚内だった訳は、「旅は北から始めるもの」と思い込んでいたからだそうです。そうして稚内市の図書室に、史実を書いた本を発見しました。古い書物には、農民たちに紐解いた「コーヒーの淹れ方、飲み方」が書かれていました。
弘前に戻った専蔵は、さっそく史実に則ってコーヒーを淹れてみました。そして飲み終わったその瞬間、「藩士の珈琲」と名づけたセレンディピティ―こそ、成田専蔵珈琲店大繁盛の始まりとなったのだとさ。おしまい。
2018年12月7日 岡 希太郎
◆最近の ピリオドの向こう側
- 2026/01/05(NO.1795) どうなる2026年 山田雄正
- 2025/12/25(NO.1794) 詐欺とクマ! 小濱綱之
- 2025/12/22(NO.1793) あなた死んでもいいですか 山田雄正
- 2025/12/17(NO.1792) なめたらいかんぜよ! 小濱綱之
- 2025/12/15(NO.1791) わが身の業も煮ゆるかな 山田雄正
- 2025/12/09(NO.1790) 生きている不思議 山田雄正
- 2025/12/08(NO.1789) スパルタ デコッパチ
- 2025/12/05(NO.1788) おなごの勘! 小濱綱之
- 2025/12/04(NO.1787) ゲイシャの味は産地による 岡 希太郎
- 2025/12/01(NO.1786) 自堕落に生きながらえて 山田雄正
>>リスト表示