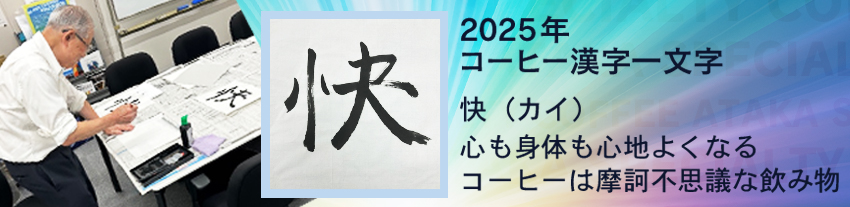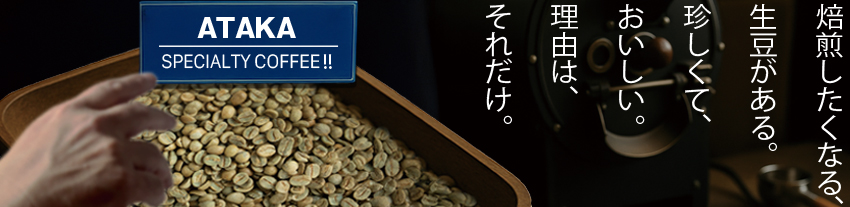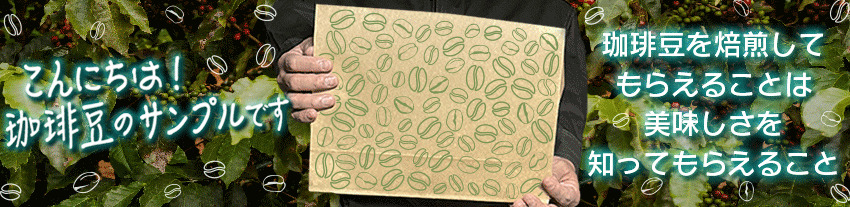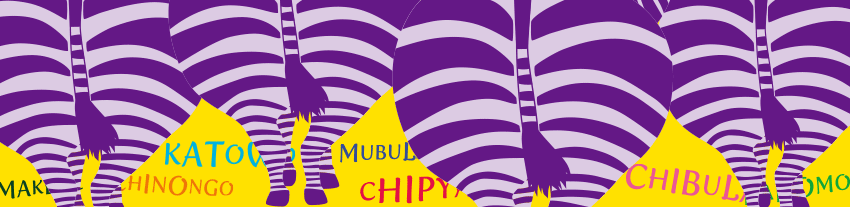2018/08/15
(NO.1119) テニスときどきウィンブルドン Decopachi
夏は、カキ氷、アイスコーヒー、ウィンブルドン、甲子園、である。
甲子園で、一時代を築いたほか、練習方法にも肩を休ませるなどの改革的実践を残した桑田真澄氏。NHKでのインタビューにおいて、甲子園でのいちばんの思い出を聞かれ、意外にも、決勝戦ではなく、1年生のときの準決勝、対池田高校戦を挙げた。先輩からは、10点取られないようはげまされ、1回、ツーアウトまで簡単に取ったが、3番、4番打者に火の出るような打球を打たれてピンチに。続く5番バッターもまた会心のピッチャーゴロが来たが、ぱっとグラブを出したら、ボールが入ったという。
あれがもし、センター前に抜けていたら今までの桑田氏はなかったと発言している。その一球が、池田時代からPL黄金時代、横浜高校時代へのシフトの契機になったようだ。
一方で、テニスの英ウィンブルドン。気候は、酷暑の日本と異なるが、伝統や、一球への審判は重い。
IT、AIと人間がどう共存していくか。そのヒントのヒントみたいなものをみた。
大会において、地元イギリスの選手はなかなか勝ち進んでこないが、ボールボーイのボールさばき、線審の立ち振る舞い、主審の威厳、大会の空気、ロイヤルボックス、休憩タイムの選手に日傘をさすスタッフ(仮設の屋根を作るという発想はないらしい)、など、他のメジャー大会とは、一線を画するものがある。ITがいくら発達しても、守るべき慣習が根強く存在している。
ラインジャッジのひとは、女子セリーナ選手の時速200キロ近いサーブを、折り目正しい姿勢を保ちつつ、見極めている。センターラインに来たときは、向かってくるボールをよけつつ、フォルト!!と、瞬時に叫ぶ。
一方、そこかしこでITの台頭は目立つ。まずは、サーブがネットにかすったときにピーッと音がする。また、試合が終わったあと数分でA Iが編集版を作ってしまう。AIは映像から「Excitement Level(盛り上がり度)」を独自の基準で判定し、その基準を超えた試合のハイライト映像を自動で生成する。主催者のホームページの洗練度、無料でみれる映像群の量・質において、日本ではなかなか匹敵するHPは現時点でないのではないかと思う。
次に、チャレンジ。数回まで、選手はボールのフォルト判定に対して、ITによる再審(チャレンジ)を請求できる。男子準決勝の第4セットのセットポイントでは、チャレンジにより、アウト判定がインに覆り、スペインのナダル選手の第4セット奪取となった。
数年ぶりにじっくりとテニスをみたが、選手の顔触れが大きく変わっていたり、ジョコビッチが復活したり、ドイツの女子選手がドイツ的に優勝したり、スライス主体で攻めるチェコの女子選手がいたり、見えないようなサーブを打つマッチョな選手が錦織選手と対戦するなど、多種多彩である。優勝したジョコビッチは、おとなしい帰宅部の高校生男子みたいな風貌。すごい体格や筋肉をしているようにみえないのに、正確で、強い。しぶとい。とにかく拾う。絶対絶命のピンチを、しばしばひっくり返す。
サッカーみたいにガチンコでぶつかったり、引っ張ったり、すねを削りに行ったり、という行為はないが、テニスも結構格闘技的な要素がある。しかし、体当たりや、レッドカードにつながるような反則や、露骨なラフプレーがないことから、わたしは、テニスにたいして、サッカーよりも少し親和的な気持ちになってしまう。スカッシュみたいに、ミスに嘆き、吠える人もあまりいなさそうだ。しかし、伝統は羨ましい。国際試合のテニスの審判の数はラインズマン含めて7人。スカッシュなんぞは3人である。ちなみに山登りは自己責任、ゴルフは同組のマーカーなどなど、スポーツごとに審判の存在感はことなる。ウィンブルドン準決勝で、ジョコビッチはミスをしても紳士的であった。スカッシュが、テニスに匹敵する地位に近づくには、あと100年くらいかかりそうだ。
テニスで、もしロボット同士が打ち合うようになったら、世も末になろう。人間が、人間とも思えないスピードのサーブをしたり、ピンポン球みたいな曲がり方をするドライブボールを打ったり、機械のように淡々と相手の決め球を打ち返したり、ロブでとりあえず逃げたり、フォルトに嘆いたりするから面白い。極めて人間的なスポーツだと思う。酷暑が続くが、ひさびさに、すきなスポーツをみれて、小さくも確かな幸せであった。ちなみに、甲子園においては、投手の投球数制限制度、チャレンジ制度、などが実現してくれたらと思う。甲子園で燃え尽きる選手がもう出ないようにと切に願う。
2018年8月15日 Decopachi
◆最近の ピリオドの向こう側
- 2026/01/06(NO.1796) コーヒーノキの起源 岡 希太郎
- 2026/01/05(NO.1795) どうなる2026年 山田雄正
- 2025/12/25(NO.1794) 詐欺とクマ! 小濱綱之
- 2025/12/22(NO.1793) あなた死んでもいいですか 山田雄正
- 2025/12/17(NO.1792) なめたらいかんぜよ! 小濱綱之
- 2025/12/15(NO.1791) わが身の業も煮ゆるかな 山田雄正
- 2025/12/09(NO.1790) 生きている不思議 山田雄正
- 2025/12/08(NO.1789) スパルタ デコッパチ
- 2025/12/05(NO.1788) おなごの勘! 小濱綱之
- 2025/12/04(NO.1787) ゲイシャの味は産地による 岡 希太郎
>>リスト表示