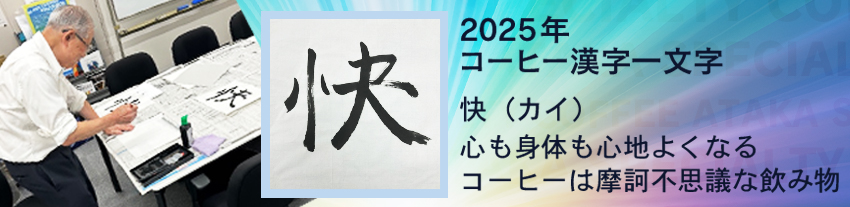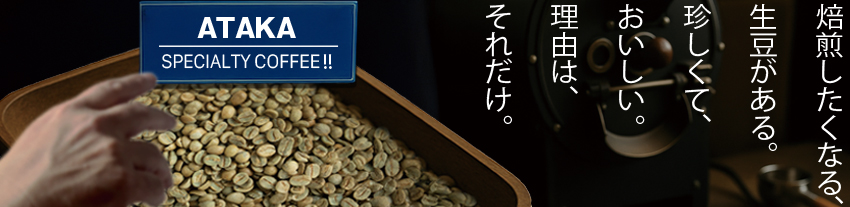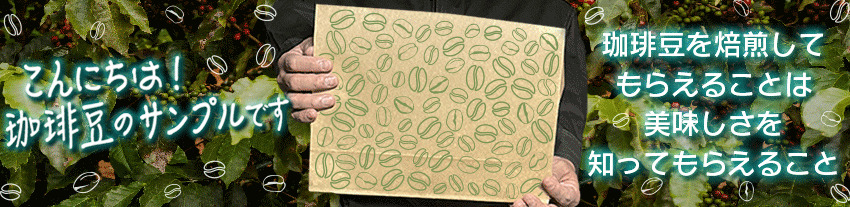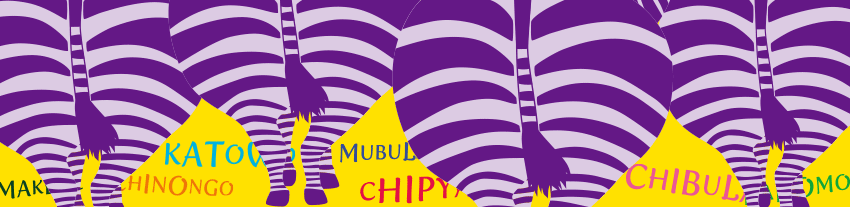2018/06/27
(NO.1110) 羊と鋼 Decopachi
明るく静かに澄んで懐かしい文体、少しは甘えているようでありながら、きびしく深いものを湛えている文体、夢のように美しいが現実のようにたしかな文体(原 民喜)
羊と鋼の森という映画をみた。最初、この題名をみたときは、硬質な題名から、モンゴルの砂漠や森を舞台とした戦争映画かと思ったら、大違い。青年が一人前のピアノ調律師に育っていく過程の物語であった。本を先に読み、映画化を心待ちにしていた人に怒られよう。わたしが、あした、もし死んでいたら、ピアノというものは、羊毛のフェルトの付いた木製のハンマーが、弦を叩くことによって、初めて音が出るということを知らないまま死ぬところであった。静かな森のにおいがする映画だ。
ひとりの高校生が、放課後ボーっとしていたら、先生から、お客さんを体育館のグランドピアノまで案内するように言われる。最初はまったく無関心であったが、とりつかれたように、ニ時間ほどの調律作業に引き込まれ、調律の音を聴き、子供の頃からみてきた森林の音、木々のざわめきを思い出し、共鳴し、調律師を天職とすることを決める。
その後、家族を説得し、専門学校のために上京する。卒業後、すぐに故郷にもどり、学校で最初出会った調律師(三浦友和)が経営する楽器店に就職し、見習いから始め、いろいろなピアノを調律していく。ジャズバーのピアニスト、コンテストを目指す高校生姉妹、ピアノ再開をようやく決意したひとなど、それぞれの要求を汲んでいかなくてはならない。
本は読んでいないのだけど、きっとすてきな文体なんだろうなと思う。映画は、きっと本の全部を描き切れないのだろうが、映画には、なんといっても音がある。曲が迫ってくる。とびこんでくる。耳から頭の中を通り、内臓や肌に入り込んでくる。ピアノに少し、くびったけになる映画である。映画をみたあと、ピアノの名曲の何曲かをあらためて聴きなおすことになった。
華やかではないかもしれないけど、この主人公のように、天職をみつけ、職人として生きていく姿は、心底から羨ましいと思う。真から思う。
映画の行間が知りたくなり、少し、原作を立ち読みしてみた。こちらがオリジナルなのだから、当たり前なことなのだが、行間どころか、映画では書かれていなかったこと、映画のイメージの容積を膨らます描写が、ふんだんに書いてある。そのような文章、箇所を読むたびに少しばかり驚喜している。冒頭の10分程度の映像のなかだけでも、映画では語られていないセリフ、心象風景が、本の中にいくたもあるのだ。原作をたまらなく読みたくなる映画であった。逆に、オリジナルが映像・音にどのように集約され、変わったかをみつけ、映画だからこその超越性、限界を確認できると思う。
2018年6月27日 Decopachi
◆最近の ピリオドの向こう側
- 2026/01/05(NO.1795) どうなる2026年 山田雄正
- 2025/12/25(NO.1794) 詐欺とクマ! 小濱綱之
- 2025/12/22(NO.1793) あなた死んでもいいですか 山田雄正
- 2025/12/17(NO.1792) なめたらいかんぜよ! 小濱綱之
- 2025/12/15(NO.1791) わが身の業も煮ゆるかな 山田雄正
- 2025/12/09(NO.1790) 生きている不思議 山田雄正
- 2025/12/08(NO.1789) スパルタ デコッパチ
- 2025/12/05(NO.1788) おなごの勘! 小濱綱之
- 2025/12/04(NO.1787) ゲイシャの味は産地による 岡 希太郎
- 2025/12/01(NO.1786) 自堕落に生きながらえて 山田雄正
>>リスト表示