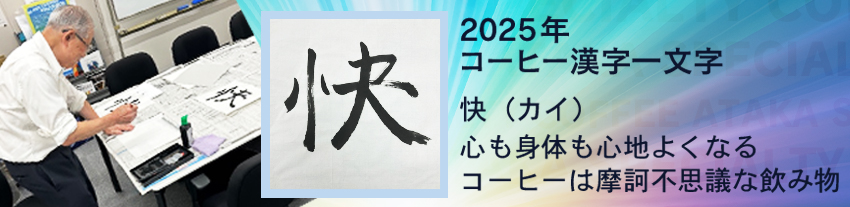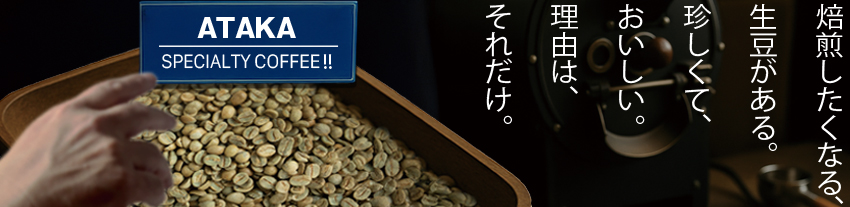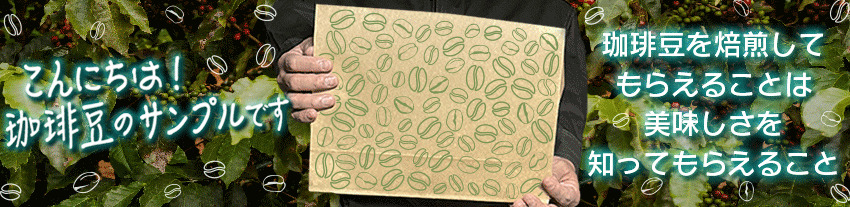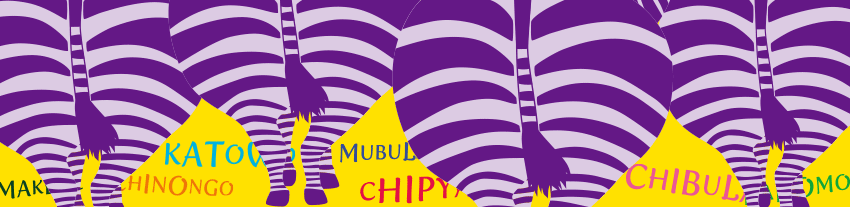2018/06/04
(NO.1105) つくば山 Decoppachi
山に行く時、「どこの山に登るか迷ったら箱根の金時山」を信条としてきたが、これからは、「迷ったら筑波山!」にします。
高さは千米に満たないが、頂上近くからの景色は息をのむばかりである。
日本百名山のなかでもっとも標高は低いだろえ。しかし、歴史や信仰や品格に満ちて、あふれている。
ちなみに、日本百名山を書いた深田久弥は歴史の古さをあげる。昔、御祖(みおや)の神が所々の神のもとを廻った際、日が暮れて富士山に着き、宿を求めたら富士の神に断られた。御祖の髪は富士山は雪や霜に閉じ込めようぞ、と言い残し、東の方へ行くと筑波山があった。そこでは暖かく迎えられ、歓待された。御祖の神の喜びこの上なく、日月と共に幸あれ、などの言葉を送ったという。
ケーブルカーなどを使わなければ、いくつものコースがあり、往路2時間ほどのコースもある。
今回往路はその2時間のコースを辿ったが、苔むした静かな道や、岩だらけの素敵な少し急坂の道、急な岩場など、たおやかなバランスで、いろいろな種類の趣きを持った往路であった。道も荒れていない。
素敵な岩場? この表現を妙に感じるひともいようが、このような、登りやすすぎるほど簡単でなく、一方でひとを拒絶するような威圧感がない、といった岩場がちの山道はめったにない。きっと管理するひとたちによる整備も行き届いているのだろう。古くから修験者の山でもあり、そこかしこにその足跡らしき跡も見られるほか、数トンの岩が数ミリ単位の微妙なバランスで昔から宙に浮いているような空間をくぐっていく場所も登路上にある。こうしてみると、この山の山道の石は小石から巨岩まで、すべての石や岩に、古来の神が宿っているようである。
素晴らしい、いい山であった。しかし、復路はケーブルカーを使って降りてしまった。まったくの邪道である。そのせいか、そのあとは、体調を崩すなど難ばかりである。どうも信仰深い山を登ると、そのあとはえらい目にあうことが、経験的にすこし目立つ。わたしがキリスト教系の学校に通っていたので、なにかがガチンコしているのだろうか。しかし、祠のある山や、信仰的な山は、これからもわんさかあろう。日本古来の神々と縁の深い山に登ることは何回もあろう。その度に倒れていたら身がもたない。さてさて、困った。ほんとうに困った。しかし、自分の体を使った検証を含めて、これからも時々山行しなくては。コーヒーだって違う国同士のブレンドがあろう。やはり、これからも登ってから考えることにしよう。なるようになれ、である。
2018年6月2日 Decoppachi
◆最近の ピリオドの向こう側
- 2025/12/17(NO.1792) なめたらいかんぜよ! 小濱綱之
- 2025/12/15(NO.1791) わが身の業も煮ゆるかな 山田雄正
- 2025/12/09(NO.1790) 生きている不思議 山田雄正
- 2025/12/08(NO.1789) スパルタ デコッパチ
- 2025/12/05(NO.1788) おなごの勘! 小濱綱之
- 2025/12/04(NO.1787) ゲイシャの味は産地による 岡 希太郎
- 2025/12/01(NO.1786) 自堕落に生きながらえて 山田雄正
- 2025/11/26(NO.1785) まともじゃない! 小濱綱之
- 2025/11/25(NO.1784) 遠い時代の人ばかり 山田雄正
- 2025/11/17(NO.1783) 若いふたり 山田雄正
>>リスト表示